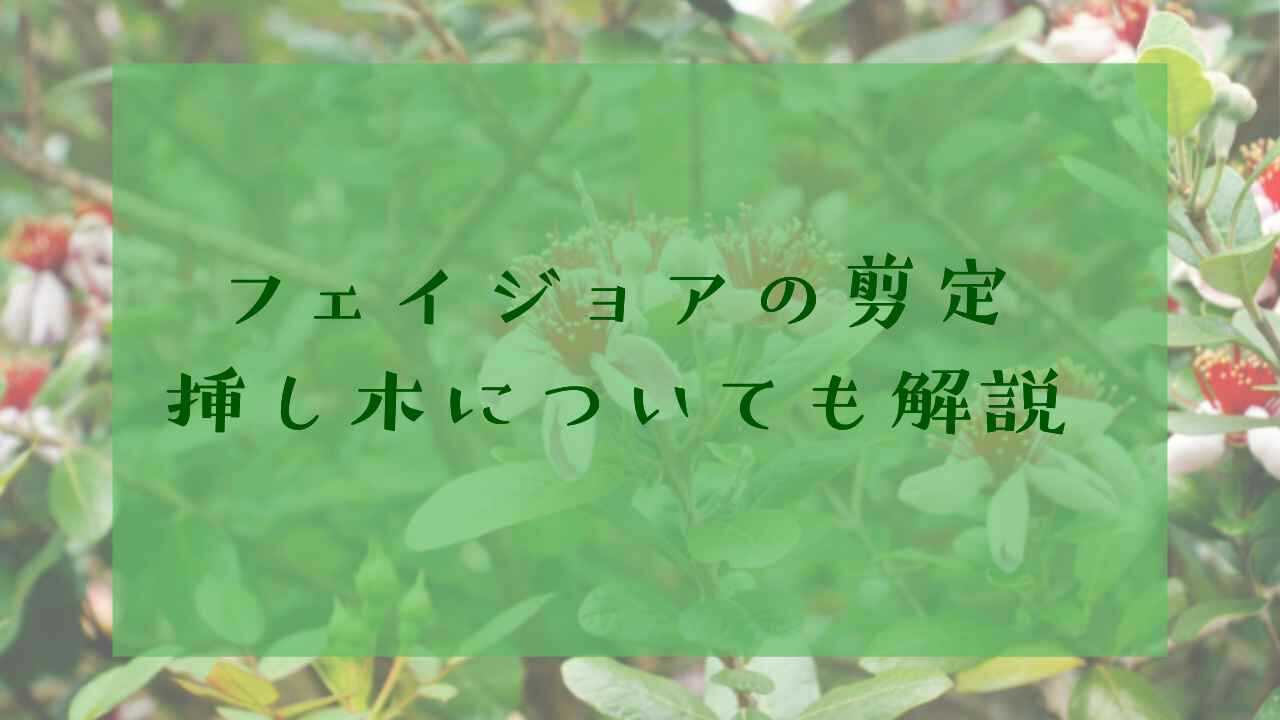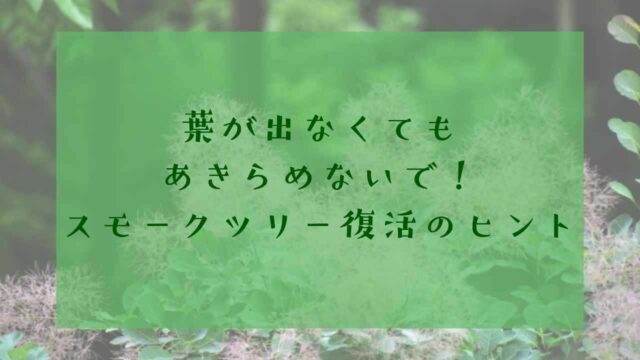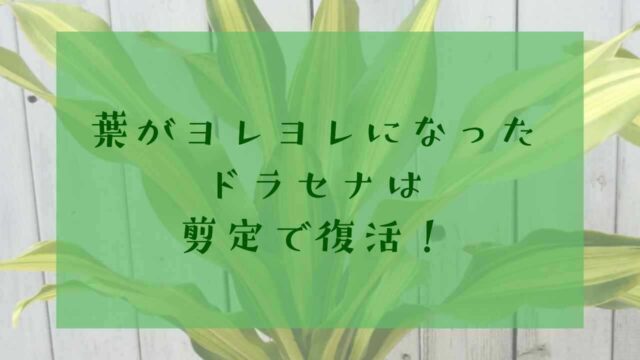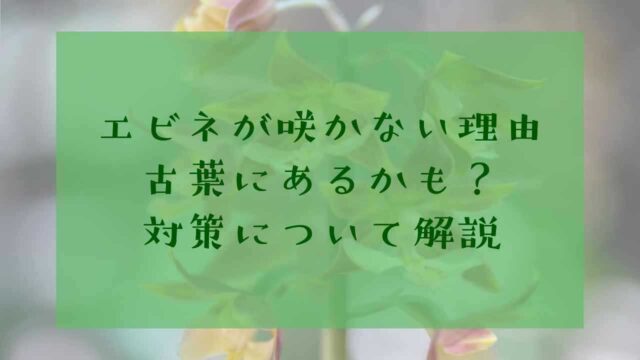フェイジョアは香り高い実と美しい花が魅力の果樹ですが、樹形を保ち、花や実のつきを良くするためには「剪定」が欠かせません。さらに、剪定で切り取った枝は「挿し木」に利用すれば、新しい苗木として育てられます。
この記事では、フェイジョアの切り枝を活用した剪定・伐採のコツと、挿し木や水差しによる繁殖方法を、初心者にも分かりやすく解説します。失敗しにくいタイミングや注意点も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
フェイジョアの剪定・伐採が必要な理由
フェイジョアは南米原産で、オーストラリアやニュージーランドでも広く栽培されている常緑果樹です。日本では比較的暖かい地域や、関東以南の庭木として人気があります。
樹高は放置すれば3〜5mまで成長し、枝葉が密集していくため、放任栽培では花や実の付きが悪くなりやすい特徴があります。ここでは、なぜ剪定・伐採が必要なのか、その3つの主な理由を詳しく見ていきましょう。
1. 樹形を整えるため
フェイジョアは成長が早く、枝が四方に勢いよく伸びます。自然樹形も魅力ですが、枝同士が絡み合うと、見た目が乱れるだけでなく、管理作業がしづらくなります。特に狭い庭や鉢植えでは、スペースを有効に使うためにも樹形のコントロールが不可欠です。
理想的な樹形は、中心がやや開いた「開心形」や、果樹全般でよく使われる「主幹形」です。これにより光が均等に入り、下枝まで元気に育ちます。
2. 実付き・花付きの改善
フェイジョアの花芽は前年に伸びた枝に付きます。枝が混み合って光が不足すると花芽の形成が弱まり、花の数も減少します。結果として、収穫量や果実の品質が下がります。
剪定によって内部まで日光が届くようにすれば、光合成が活発になり、果実が甘く香り高く育ちます。また、余分な枝を減らすことで、残った枝や果実に栄養が集中し、一つひとつの実が大きく育ちます。
3. 病害虫の予防
枝が密集して風通しが悪くなると、湿気がこもって病害虫が発生しやすくなります。特に梅雨時や秋雨の季節は、灰色かび病や炭疽病などの真菌性疾患が発生しやすくなります。
フェイジョアの特徴
フェイジョアの特徴のひとつは、枝の伸び方が比較的まっすぐで、横枝よりも縦に成長する傾向が強いことです。そのため、若木のうちは枝数が少なくても樹高がどんどん伸びてしまい、上の方ばかり葉が茂る「ほうき状樹形」になりやすいという弱点があります。
この状態では下枝や内部が日陰になり、花芽がほとんどつかなくなってしまいます。他の果樹(例:柿や桃)のように強めの剪定に耐える性質を持っているため、若いうちは思い切って上部の枝をカットし、横枝を充実させることが重要です。こうすることで光合成が効率的になり、安定した収穫につながります。
また、フェイジョアは一部の品種が自家結実性を持ちますが、多くは異なる品種同士の受粉が必要です。そのため、剪定で樹形を整えて人工授粉しやすい形にしておくことも、果実収穫には大きな意味があります。
フェイジョアの切り枝の正しい剪定時期
剪定のタイミングは、樹木の健康や翌年の収穫に直結します。フェイジョアは常緑樹で一年中葉を付けていますが、花芽の形成時期や樹液の流れを考慮して計画的に作業する必要があります。
1. 生育サイクルと剪定の関係
フェイジョアは春(4〜5月)に新芽を伸ばし、6月頃に花を咲かせます。その後、果実は夏から秋にかけて肥大し、晩秋(10〜11月)に収穫期を迎えます。このサイクルを踏まえると、花芽や実を傷つけない時期に剪定することが重要です。
2. 実を楽しみたい場合のベストタイミング
最も適した時期は、晩秋から冬(11〜2月頃)の休眠期です。この時期は樹の活動が鈍く、切り口の回復が早い上に、花芽を落とすリスクが少ないです。
また、冬剪定では「不要枝の間引き」「枯れ枝や病枝の除去」「樹形の整理」を中心に行いましょう。
3. 樹勢が強すぎる場合の対処
フェイジョアは年によって成長の勢いが異なり、特に雨量や気温が高い年は枝が過剰に伸びることがあります。この場合、夏の軽剪定(7〜8月)で混み合った枝を少し間引くと、風通しや日当たりが改善されます。ただし、夏剪定では花芽や果実を誤って切らないように注意が必要です。
切り枝の剪定・伐採のコツ
剪定作業は、ただ枝を切ればよいわけではありません。切り方や道具の使い方ひとつで、樹木の健康や翌年の収穫に大きな差が出ます。
1. 道具の選び方(剪定バサミ・ノコギリ)
- 剪定バサミ:直径2cm以下の枝向け。切れ味が良いものを選び、作業前後にアルコールや次亜塩素酸水で消毒します。
- 園芸用ノコギリ:太い枝(2cm以上)を切る際に使用。刃の細かさや切れ味が重要で、引き切りタイプが扱いやすいです。
- 癒合剤:切り口を保護して病気を防ぎます。
2. 枝の切り方(太い枝・細い枝の処理)
- 細い枝:葉芽の上5mm程度で、斜めに切ります。切り口が水平だと水が溜まりやすく、腐敗の原因になります。
- 太い枝:いきなり切ると枝の重みで裂けるため、「3段階切り」(下切り→上切り→仕上げ切り)を行います。
3. 切った後の処理と注意点
切り口は必ず癒合剤を塗り、雨の日や湿度が高い日に作業するのは避けます。特に梅雨前や秋雨前線の時期は要注意です。また、剪定くずは放置せず、病害虫の温床にならないよう速やかに処分します。
4.切るべき枝の見分け方
剪定時に迷いやすいのが、「どの枝を切って、どの枝を残すべきか」という判断です。基本的な目安は以下の通りです。
- 切るべき枝:内向きに伸びている枝、交差している枝、枯れ枝、病害虫の被害枝、極端に長く伸びすぎた徒長枝
- 残すべき枝:外向きに健康的に伸びている枝、前年に伸びた実績のある枝、花芽が確認できる枝
特に内向き枝は樹冠内部を暗くしてしまい、湿気や病気の原因になります。外向きの枝を残して空間を作ることで、光と風が入りやすくなり、翌年の花付きも改善します。
もうひとつのポイントは「芽の向き」。切る位置のすぐ下にある芽が、将来どちらに伸びるかを考えてカットします。外芽の上で切れば枝は外側に広がり、内芽の上で切れば中心方向に伸びます。基本は外芽を意識して剪定すると樹形が整いやすくなります。