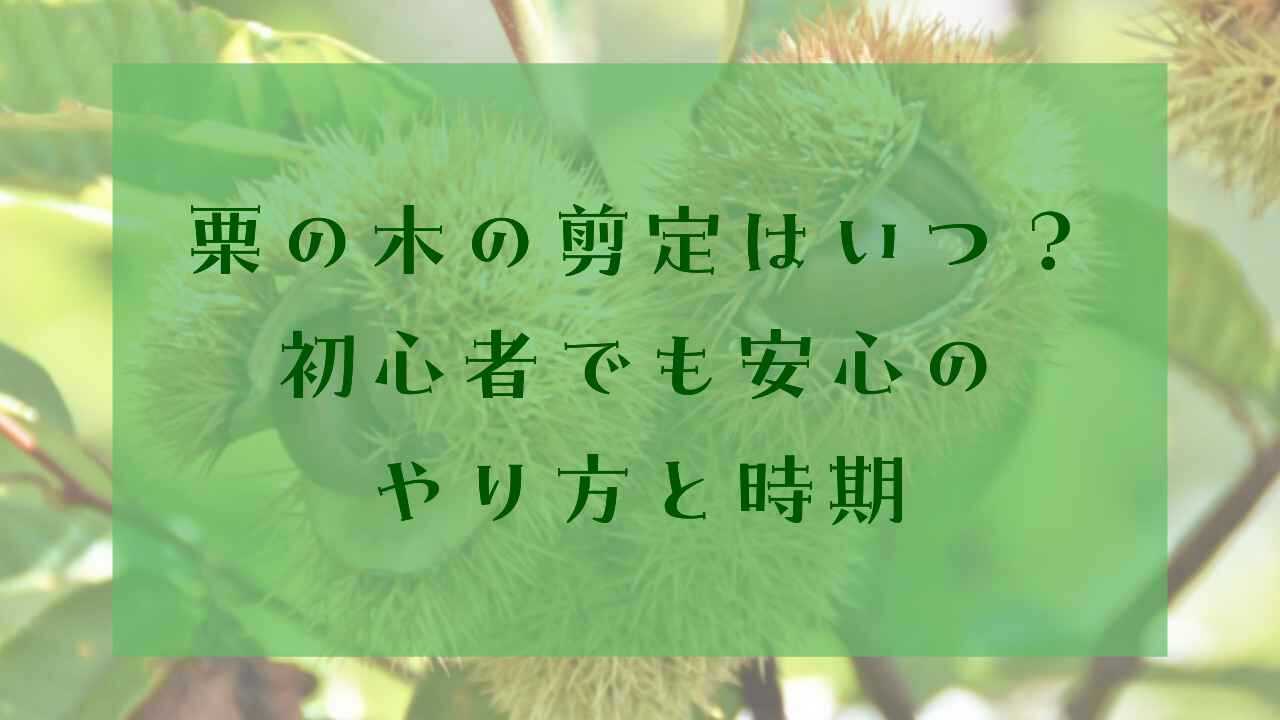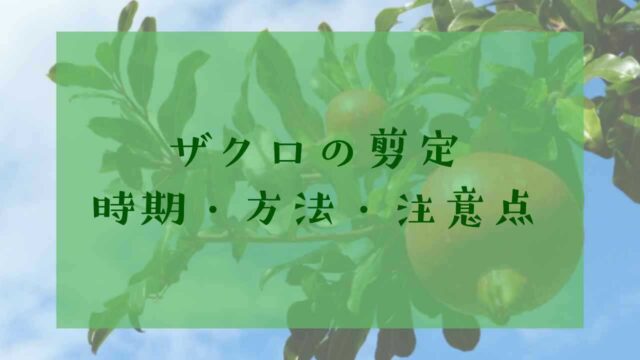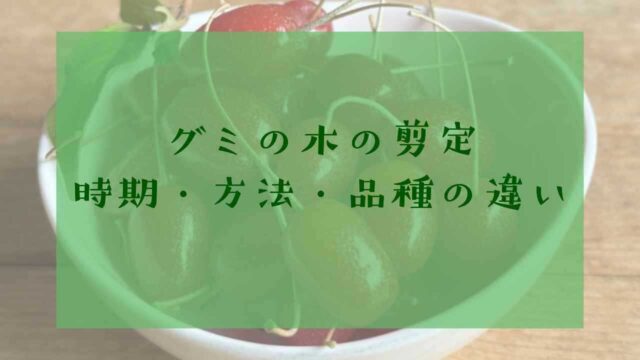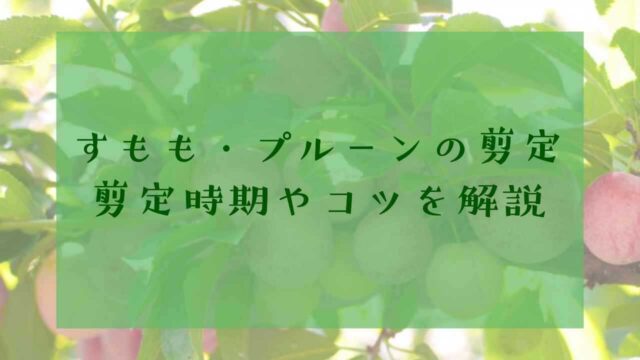本記事では、初心者でも安心して取り組める剪定方法や時期、失敗しないためのコツをわかりやすく解説します。自力での作業が難しいと感じた方には、業者に頼む選択肢も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
栗(クリ)とは?主な品種についても解説

栗(クリ)は、ブナ科クリ属に分類される落葉広葉樹で、日本では古くから親しまれている果樹のひとつです。山林にも自生しており、秋になるとイガの中に実る栗の実は、食用として多くの家庭で利用されています。木材としても利用され、耐久性が高いため、建築や家具にも使われてきました。
栗の木は生長が早く、樹高が10mを超えることもある大型の木です。日当たりと排水性の良い土地を好みますが、比較的土質を選ばないため、庭木としても人気があります。春に若葉が芽吹き、6〜7月には雄花と雌花が同時に咲き、9〜10月頃には収穫期を迎えます。
日本で栽培されている栗の主な品種
丹沢(たんざわ)
早生品種で育てやすく、実のサイズはやや小ぶりですが甘みが強く、人気があります。家庭栽培にも適しています。
銀寄(ぎんよせ)
中生品種で実が大きく、渋皮がむきやすいため加工用にも向いています。家庭用・販売用ともに人気の高い品種です。
筑波(つくば)
近年注目されている品種で、甘みがあり、品質が安定していることから商業用にも多く植えられています。剪定や育て方によって実のつき方が大きく変わるため、管理がポイントになります。
石鎚(いしづち)
晩生品種で、台風の時期を避けて収穫できるのが特徴です。果実は大きく、日持ちがするため保存にも適しています。
それぞれの品種には特徴があるため、育てる目的や地域の気候に合わせて選ぶとよいでしょう。また、栗の品種によって剪定の方法やタイミングが多少異なることもありますので、品種に合った育て方を意識することが大切です。
栗の木の剪定はなぜ必要?

栗の木は丈夫で育てやすい木ですが、健康な成長と実つきを維持するためには定期的な剪定が欠かせません。放っておくと枝が四方に伸びすぎて日当たりや風通しが悪くなり、病害虫の被害にもつながります。
また、栗の実はその年に伸びた新しい枝の先につくため、枝が混み合っていると光が届かず、実のつき方や大きさが悪くなることがあります。不要な枝を整理し、樹形を整えることで収穫しやすくなるのも大きなメリットです。
家庭で育てる場合は特に、高くなりすぎると剪定や収穫作業が難しくなるため、低めに仕立てることが望ましいです。そのためにも、剪定によって高さをコントロールしておくことが重要です。
剪定に適した時期はいつ?
栗の木を適切な時期に剪定することで、木の健康を維持しながら、翌年の実つきにも良い影響を与えられますが一方で、時期を誤ると枝が枯れたり、病害虫の侵入を招いたりするため、注意が必要です。
栗の剪定には大きく分けて「冬季剪定」と「夏季剪定」があります。それぞれに役割が異なりますので、目的に応じて使い分けましょう。
冬季剪定(1月~2月):骨格を整える時期
冬の間、栗の木は休眠期に入ります。このタイミングで剪定を行うことで、木に与えるダメージを最小限に抑えることができます。主に以下のような作業を行います。
- 不要な太枝や込み入った枝の間引き
- 高くなりすぎた枝の切り戻し
- 風通しや日当たりを改善するための枝の整理
特に「栗の木を低く保ちたい」「枝が混み合って収穫がしづらい」と感じている場合は、冬季剪定が効果的です。また、冬場は葉が落ちて枝の構造が見やすいため、初心者にも取り組みやすい時期といえます。
ただし、寒冷地では2月以降になると寒さが厳しくなり、剪定した枝の切り口から凍害を受ける恐れがあります。できるだけ1月中に済ませておくのが無難です。
夏季剪定(7月~8月):成長を抑える時期
夏の剪定は、木が活発に成長している時期に行います。そのため、樹勢をコントロールしたいときや、日当たりを改善したいときに有効です。夏季剪定では以下のような作業を行います。
- 長く伸びた徒長枝の除去
- 病害虫に侵された枝の早期処理
- 栗の実に日が当たるように枝の間引き
ただし、夏の剪定は木に与える負担が大きいため、やりすぎは禁物です。特に「栗の木 剪定 夏」のキーワードで調べると、「夏に強く切りすぎて枯れた」という失敗談が少なくありません。切り口が大きくなると、夏の高温多湿により雑菌が繁殖しやすくなるため、切る位置や量には注意が必要です。
栗の木の剪定の注意点
栗の木の剪定には、ほかの果樹や庭木とは異なる栗特有の注意点があります。間違った方法で切ってしまうと、翌年の実がつかないばかりか、病気や枯れの原因にもなります。以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。
1. 実がなる位置を理解して切る
栗の実は「その年に伸びた枝の先端」に実ります。つまり、前年に伸びた枝を深く切り戻してしまうと、今年の結実場所が失われるということです。実をつけさせたい年には、前年の枝先をなるべく残すようにしましょう。
逆に言えば、間引きや切り戻しを行うなら、実を収穫した直後〜休眠期(冬)にかけて行うのが理想です。これにより、春に新しい芽が出やすくなり、結果的に来年の実つきを助けます。
2. 切り口が大きくなりすぎないようにする
栗の木は傷口(切り口)から病原菌が入りやすい性質があります。とくに炭疽病(たんそびょう)や胴枯病は栗の木にとって致命的な病害です。太い枝を切るときは、必ず斜めに切り、切り口に癒合剤を塗布しましょう。
また、雨の直前や湿度の高い日に剪定を行うと、雑菌の繁殖を助けてしまいます。乾燥した晴天の日を選び、作業後の消毒や清掃まで丁寧に行うことが大切です。
3. 栗の木のヤニ(樹液)に注意する
栗の木は剪定後にヤニ(樹液)がにじみ出ることがあります。これを放置すると、傷口からの病原菌の侵入を促すだけでなく、昆虫を呼び寄せる原因にもなります。にじみが多い場合は、軽く拭き取ってから癒合剤をしっかり塗りましょう。
また、樹液が手や道具につくとベタついて扱いにくくなるため、剪定用の手袋と工具のメンテナンスもきちんと行いましょう。
4. トゲとイガに注意して作業する
栗の木には、若い枝に鋭いトゲが生えることがあります。特に夏季剪定時や収穫後の剪定では、イガが残っている可能性もあり、作業中に手や腕を傷つけてしまう危険があります。必ず厚手の手袋と長袖を着用し、安全に配慮した服装で作業しましょう。
5. 高木化した栗は無理に自分で剪定しない
栗の木は放っておくと10メートル以上にも成長します。高所の枝を無理に脚立で剪定しようとすると、バランスを崩して落下する事故のリスクが非常に高まります。また、上からの剪定は切り口も不安定になり、病害虫の侵入も増える原因になります。
もしすでに高木化してしまっている場合や、自分で作業するのが不安なときは、剪定・伐採の専門業者に依頼することを検討しましょう。
栗の木を低く育てるコツと切り戻しの方法
家庭の庭や狭い畑で栗の木を育てる場合、木を低く保つことが管理のしやすさや収穫のしやすさにつながります。栗の木は成長が早く、放っておくと10メートル以上にもなってしまうため、早い段階から「低木仕立て」を意識した育て方をすることが大切です。
ここでは、栗の木を低く育てるためのポイントと、具体的な切り戻しの方法を紹介します。
主幹を立てずに開心自然形に整える
栗の木を低く育てるには、「開心自然形(かいしんしぜんけい)」という剪定スタイルがおすすめです。これは、真ん中の主幹(中心の太い幹)を切って、複数の側枝を放射状に広げる樹形で、高さを抑えつつ日当たりや風通しを良くすることができます。
苗木の段階で主幹を地面から50〜80cmくらいの高さで切り戻し、そこから出てくる側枝を3〜4本だけ残して横に広げていくのが基本です。これにより、初期段階から高さを制御しながら育てられ、収穫や剪定もしやすくなります。
切り戻しのタイミングは冬がベスト
「栗の木 切り戻し」を行う最適なタイミングは、1月から2月の休眠期です。この時期は葉が落ちて枝の構造が見えやすく、切るべき枝を見極めやすくなります。また、木が活動を停止しているため、剪定によるダメージが少なくて済みます。
切り戻す際は、前年に伸びた枝の先を1/3〜1/2ほど切るのが基本です。これにより、翌春に新芽が吹き出しやすくなり、同時に高さも抑えられます。ただし、切りすぎると枝が枯れたり、木が弱ってしまうことがあるので、強剪定は数年かけて段階的に行うのが安全です。
木の上部ばかり切らないように注意
高さを下げようとして、ついつい上部の枝ばかりを剪定してしまいがちですが、これは危険です。上を切りすぎると、逆に木が防御反応で新たな徒長枝(無駄に長く伸びる枝)を勢いよく出し、高さが余計に増してしまうことがあります。
そのため、上部と同時に下部の不要な枝も整えることが大切です。全体のバランスを見ながら、樹冠(枝葉の広がり)を水平に近い形で保つよう心がけましょう。
大きくなりすぎた場合は段階的に対応を
すでに大きく育ってしまった栗の木を一気に低くするのは、木にとって大きなストレスとなります。切り口が太くなることで病気や枯れのリスクも増すため、3年〜5年ほどの期間をかけて少しずつ高さを落としていくのがベストです。
毎年少しずつ不要な太枝を整理しながら、主軸となる枝を段階的に切り戻していくことで、木を弱らせることなく理想の高さに近づけることができます。
栗の木の剪定でよくある失敗とその対処法
栗の木の剪定は、果樹の中でも特に繊細な配慮が必要です。見よう見まねで切ってしまうと、翌年にまったく実がならなかったり、枝が枯れてしまったりといったトラブルにつながることもあります。ここでは、栗の木の剪定でありがちな失敗とその具体的な対処法を紹介します。
剪定のしすぎで実がつかない
最も多い失敗のひとつが、「剪定しすぎた結果、実がつかなくなった」というケースです。先にも触れた通り、栗の実はその年に伸びた新しい枝の先端につくため、前年の枝を切り詰めすぎると、実をつける場所自体がなくなってしまいます。
【対処法】
次の年はあえて剪定を控えめにし、枝数を増やすことに専念しましょう。切るなら、徒長枝や枯れ枝の整理だけにとどめるのが無難です。また、来年以降に備えて剪定のバランス感覚を見直すことが大切です。
切り口が大きくて病気になる
栗の木は切り口から病原菌が入りやすい木です。太い枝を勢いよく切ってしまった結果、傷口がふさがらずに病気になるという事例も少なくありません。とくに炭疽病や胴枯病に発展すると、木の大部分が枯れることもあります。
【対処法】
大枝を切る場合は、斜めにカットして水はけをよくするとともに、切り口には必ず癒合剤を塗布しましょう。剪定後に雨が降りそうなときは、応急処置としてビニールで覆っておくのも一つの方法です。
夏剪定で木が弱る
「夏に伸びすぎたから切っておこう」と考えて強めに剪定したところ、葉がほとんどなくなってしまい、光合成ができずに木が弱ってしまうことがあります。また、真夏の高温下での剪定は木にとって大きなダメージになる可能性があります。
【対処法】
夏は軽めの枝すかしだけにとどめ、葉が多く残るように意識しましょう。本格的な剪定は冬に行うようにし、夏は必要最低限の整理にとどめるのが基本です。
枝の切り方が悪くて芽が出ない
栗の木の枝を切るときに、切る位置が悪くて新芽が出ないというトラブルも起こります。芽の上で切るのが基本ですが、切り口があまりにも近すぎたり、逆に遠すぎたりすると、うまく芽吹かずに枝が枯れてしまうことがあります。
【対処法】
枝のすぐ上にある外芽の2〜3mm上を斜め(角度は約30〜45度)にカットするのが正しい方法で、こうすることで水がたまらず、芽が育ちやすくなります。
高所剪定で事故やケガ
栗の木は放っておくと非常に高くなるため、脚立を使った高所作業中に転倒する事故が報告されています。特に高齢の方が無理に作業することで、落下や道具によるケガのリスクが高まります。
【対処法】
高木になってしまった場合は、無理に自分で剪定せず、剪定業者に相談するのが安全です。プロであれば、高所でも専用の道具と技術で効率よく作業を行ってくれます。
まとめ|正しい剪定で栗の木を健康に育てよう
こちらの記事では栗の木の剪定について解説しました。
- 栗は、その年に伸びた枝に実がつくため、剪定の場所とタイミングが重要
- 枝が混み合うと、実つきが悪くなったり病害虫が発生しやすくなるため、定期的な剪定が必要
- 高さを抑えるには、若いうちから低めの仕立てを意識した切り戻しが効果的
- 高木化や剪定が不安な場合は、無理せず専門業者に相談しよう
あなたの庭の栗の木が、これからも元気に実をつけてくれることを願っています。