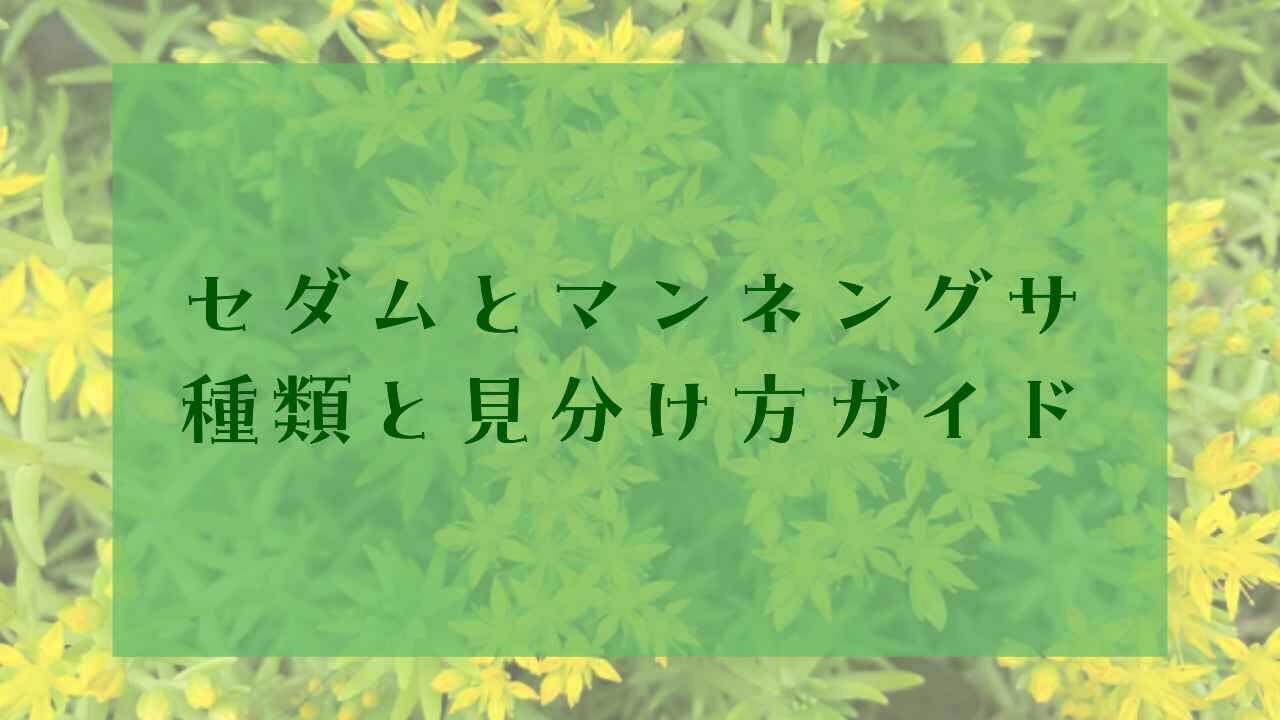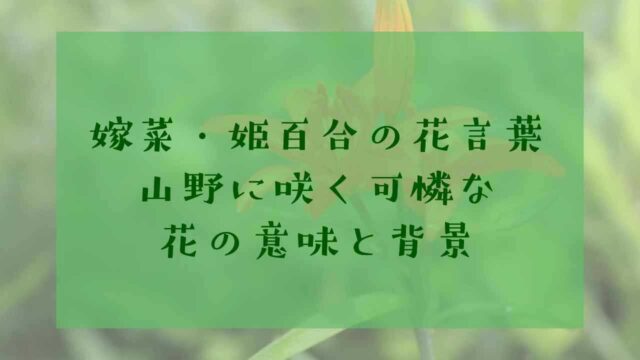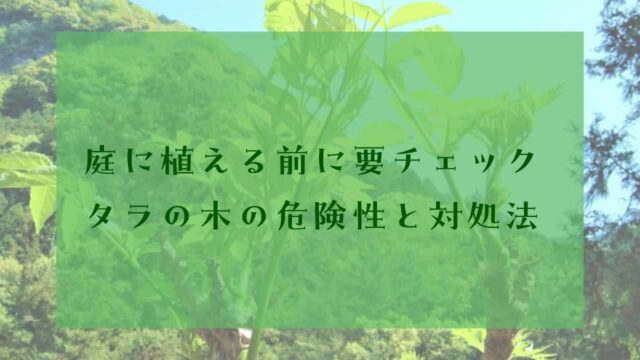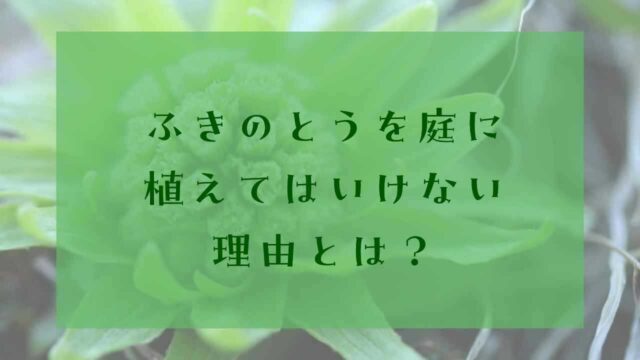庭や鉢植えでよく見かける小さな多肉植物「マンネングサ」。一見かわいい見た目ですが、放っておくとどんどん広がり、雑草のように扱われることもあります。
この記事では、セダムとマンネングサの違いから、代表的な種類、増やし方、そして増えすぎたときの対処法まで詳しく解説します。自宅の庭に合う種類を知り、上手に育てるコツをつかみましょう。
セダムとマンネングサの違いとは?見分け方の基本

セダムとマンネングサはどちらもベンケイソウ科に属する多肉植物で、見た目がよく似ているため混同されがちです。ですが、厳密にはセダムという大きなグループの中に「マンネングサ」という種類が含まれています。つまり、マンネングサはセダムの一部であり、関係は“属と種”のようなものです。
見た目の違い
セダムは世界中に400種類以上存在し、葉の形や色が多様です。対してマンネングサはその中でも日本原産または古くから日本で育てられてきた種類で、小さく密集した葉や這うように地面を覆う性質、黄色い星形の花が特徴です。
育ち方の違い
セダム全体は乾燥に強く、鉢植えでも庭植えでも育てやすい種類が多いのに対し、マンネングサは地を這ってどんどん広がるタイプが多く、グランドカバーとしてよく利用されます。その反面、繁殖力が強いため放置すると「雑草化」して他の植物を覆ってしまうこともあります。
見分け方のポイント
- 葉のサイズと形:マンネングサは葉が小さく密集している。
- 花の色:マンネングサは黄色い花が多い。
- 生え方:地を這って広がる傾向が強い。
このように、セダム=多肉植物のグループ、マンネングサ=その中で特に日本で親しまれている匍匐性タイプ、と覚えると分かりやすいでしょう。
マンネングサの種類一覧|人気・珍しい品種を紹介
マンネングサには非常に多くの種類があり、園芸用に利用されるものから、雑草として扱われるものまで様々です。ここでは特に人気が高く、庭で見かける代表的な種類を紹介します。
マンネングサの種類について
モリムラマンネングサ(Sedum morimurae)
最もポピュラーな品種で、鮮やかな緑の葉が地面を美しく覆います。乾燥や寒さに強く、グランドカバーとして広く利用されています。日当たりを好み、半日陰でも育つ丈夫さが魅力です。ただし、根が強く張るため放置すると他の植物のスペースを奪うことがあります。
メキシコマンネングサ(Sedum mexicanum)
明るい黄緑色の細い葉が特徴。成長が非常に早く、庭に植えると一気に広がるタイプです。暑さに強い反面、寒さにはやや弱い傾向があります。暖地では常緑性で、黄色い花をたくさん咲かせる姿が人気です。
ツルマンネングサ(Sedum sarmentosum)
半日陰でもよく育つ種類で、他のマンネングサよりも茎が長く伸び、壁面や鉢の縁から垂れる姿が美しいです。湿った場所にも耐えるため、庭の縁や石垣に向いています。ただし、根の張りが強く、一度根づくと除去が難しい点に注意が必要です。
コモチマンネングサ(Sedum bulbiferum)
小さな子株(むかご)を葉の間につけて増えるユニークな種類。自然に落ちたむかごが地面で根づくため、繁殖力が非常に強いです。かわいらしい見た目ですが、管理しないとあっという間に庭全体に広がります。
これらのマンネングサは見た目が似ているため、見分け方のコツを押さえると管理がぐっと楽になります。特にモリムラマンネングサは園芸用、メキシコマンネングサやツルマンネングサは自然環境にも強く、雑草化しやすいタイプと覚えておくと安心です。
モリムラマンネングサの特徴と育て方
モリムラマンネングサは、セダムの中でも特に人気が高い品種です。小さな葉が密に茂り、まるで緑のじゅうたんのように地面を覆う姿が美しく、手間もかからないためガーデニング初心者にもおすすめです。
モリムラマンネングサの特徴
モリムラマンネングサは常緑性の多年草で、日当たりと水はけの良い場所を好みます。乾燥や寒さに非常に強く、多少の踏みつけにも耐える丈夫さが魅力です。特に春から初夏にかけての生育期には、淡い黄色の花を一斉に咲かせ、地面全体が明るく彩られます。
また、暑さにも比較的強いため、コンクリート周りや石垣の隙間などでもよく育ちます。繁殖力が非常に高いので、少量を植えても1年ほどでかなり広がるのが特徴です。
ただし、他の植物のスペースを侵食することもあるため、花壇での混植には注意が必要です。
育て方のポイント
モリムラマンネングサを健康に保つためには、次の3つのポイントを意識しましょう。
- 日当たりの良い場所に植える
日照が不足すると茎が間延びして形が乱れます。明るい場所を選びましょう。 - 水はけをよくする
多肉植物の仲間なので、過湿を嫌います。鉢植えの場合は底に軽石を敷くのがおすすめです。 - 肥料は控えめに
肥料が多すぎると徒長して見た目が悪くなります。春に少量与える程度で十分です。
増やし方
モリムラマンネングサは「挿し木」または「株分け」で簡単に増やせます。切り取った茎をそのまま土に挿しておくだけで発根し、数週間で根づきます。手軽にグランドカバーを広げたい場合にぴったりです。
ただし、放置すると隣の花壇や通路まで広がることもあります。適度に剪定して形を整えましょう。広がりすぎた場合は、無理せず業者に除去を依頼するのも一つの方法です。根が強いため、自力で完全に取り除くのは意外と大変です。
マンネングサの花と開花時期
マンネングサの魅力のひとつに、春から初夏にかけて咲く小さな花があります。花は種類ごとに微妙に形や咲く時期が異なり、見分ける手がかりにもなります。
花の特徴
多くのマンネングサは、星形の黄色い花を咲かせます。花径は約5~10mmほどと小さいですが、群生すると地面が一面黄色に染まり、とても華やかです。中には白い花を咲かせる品種(ヒメレンゲなど)もありますが、黄色い花の方が圧倒的に多い傾向です。
種類別の開花時期
-
モリムラマンネングサ:5〜6月に開花。淡い黄色の花を多数つける。
-
メキシコマンネングサ:5月頃に開花。やや早咲きで、明るいレモンイエロー。
-
ツルマンネングサ:6月頃。茎を伸ばしながら花を咲かせるため立体的に見える。
-
コモチマンネングサ:5月下旬〜6月中旬。花の数は少ないがむかごで繁殖する。
このように、開花時期や花の密度で種類を判別できることもあります。
花の後の管理
開花後は、花がらを放置すると見た目が悪くなるだけでなく、種が落ちてさらに繁殖する原因にもなります。花が終わったら早めに摘み取り、形を整えるようにしましょう。
また、株が密になりすぎると通気性が悪くなり、根腐れや蒸れの原因にもなります。年に1回は剪定して風通しを良くすることが大切です。
このように、マンネングサの花は見た目のかわいらしさだけでなく、種類を見分ける手がかりにもなります。次では「マンネングサは雑草?増えすぎたときの対策」について解説します。
マンネングサは雑草?増えすぎたときの対策
マンネングサはグランドカバーとして非常に優秀ですが、その繁殖力の強さから「雑草のように増えて困る」と感じる人も少なくありません。本来は観賞用植物として魅力的ですが、環境によっては扱いを誤ると庭全体を覆ってしまうことがあります。
雑草化する理由
マンネングサは、乾燥や踏みつけにも強く、日当たりさえあればどんな土壌でも根づくほどの強健さを持っています。さらに、
・切れた茎がそのまま根づく
・こぼれ落ちた葉やむかごからも再生する
といった生命力の高さがあるため、一度根づくと完全に取り除くのは容易ではありません。
特に以下のような環境では雑草化しやすくなります。
- 花壇や芝生のすき間に入り込む
- コンクリートの割れ目や砂利の中でも繁殖
- 放置して長期間剪定しない
こうした環境では、他の植物の生育を妨げたり、見た目が乱れたりすることがあります。
自力でできる対策
- 広がる前にカットする
茎が伸び始めた段階で早めに刈り込み、広がりを抑えます。 - 境界にストッパーを設ける
レンガやプラスチックの見切り材で、根が横に広がらないようにしましょう。 - 定期的に株分けする
密集している部分を間引くことで風通しがよくなり、過剰な繁殖を防げます。
もし庭全体を覆うほど広がってしまった場合は、根が残りやすいため、スコップで浅く掘り起こして根ごと除去することが重要です。
業者に依頼する選択肢も
地面一面に広がり、何度抜いても再生するような状態なら、除草業者や剪定・伐採の専門サービスに依頼するのも賢明です。特にモリムラマンネングサやツルマンネングサのように地下茎が強いタイプは、完全除去が難しい場合があります。
専門業者であれば、再発防止のために根の処理や防草シート施工なども行ってくれるため、庭をすっきり保つことができます。
マンネングサの増やし方|挿し木・株分け・自然繁殖
繁殖力が強いマンネングサですが、コントロールしながら上手に増やせば、美しいグランドカバーを簡単に作ることができます。ここでは、家庭でも簡単にできる3つの方法を紹介します。
挿し木で増やす方法
最も一般的で手軽な方法が「挿し木」です。
- 健康な茎を5〜10cmほどカットする。
- 下の葉を2〜3枚ほど取り除く。
- 水はけのよい土に挿して軽く押さえる。
- 明るい日陰で管理し、1〜2週間で発根。
水やりは控えめにし、土が完全に乾いたら与える程度で十分です。根づいたら日当たりの良い場所に移動させましょう。
株分けで増やす方法
春か秋に、株を掘り上げて分ける方法です。古い株をそのまま放置すると中央がスカスカになるため、更新の意味でも株分けは有効です。
スコップで軽く掘り起こし、根がついた状態で数株に分けて植え直します。すぐに定着するため、庭のデザインを変えたいときにも便利です。
自然繁殖を利用する
マンネングサは、落ちた茎や葉からでも自然に根づくほど強い植物です。鉢のふちや花壇の隙間に自然に増えることも多く、わざわざ植え替えなくても増えていく場合があります。ただし、放置すると雑草化するため、範囲を決めて管理するのが大切です。
増やすときの注意点
- 植えすぎると他の植物を覆う
- 水はけの悪い場所では根腐れの原因になる
- 株が密になったら剪定して通気性を確保
管理の手間を減らしたい場合は、定期的にトリミングするか、広がりを防ぐための花壇枠を設けておくとよいでしょう。
放置しすぎた場合は?業者に頼む選択肢も
マンネングサは丈夫で育てやすい反面、放置するとあっという間に庭全体を覆ってしまいます。特にモリムラマンネングサやツルマンネングサのような匍匐性の種類は、根が広く張るため手作業での除去が大変です。
放置で起こりやすいトラブル
- 他の植物の日光を奪い、成長を妨げる
- 密集して湿気がこもり、カビやコケが発生
- 枯れ葉や花がらが目立ち、見た目が乱れる
茎や根の一部が残るだけで再生するため、「抜いてもまた生える」状態になりがちです。このような場合は、無理に自分で取り除くよりも、剪定・伐採業者に依頼する方が確実で安全です。専門業者であれば、根の除去から再発防止の防草処理まで行ってくれるため、庭の景観を長く保てます。
まとめ|種類と性質を知って上手にコントロール
マンネングサは、丈夫で手間のかからないグランドカバーとして人気があります。しかし、繁殖力が非常に強いため、広がりすぎると他の植物を覆い尽くしてしまうこともあります。
管理のコツ
- 増えすぎる前にこまめに刈り込みを行う
- 株が密になったら間引いて風通しを確保
- 区画をレンガや見切り材で区切り、根の広がりを防ぐ
- 自力で対処が難しい場合は業者への相談も検討
植える前に種類の特徴と成長スピードを理解し、適度な距離感で管理することが、長く美しい庭を維持するポイントです。
強くて育てやすいマンネングサは、上手にコントロールすれば理想のグリーンカーペットとして楽しめます。