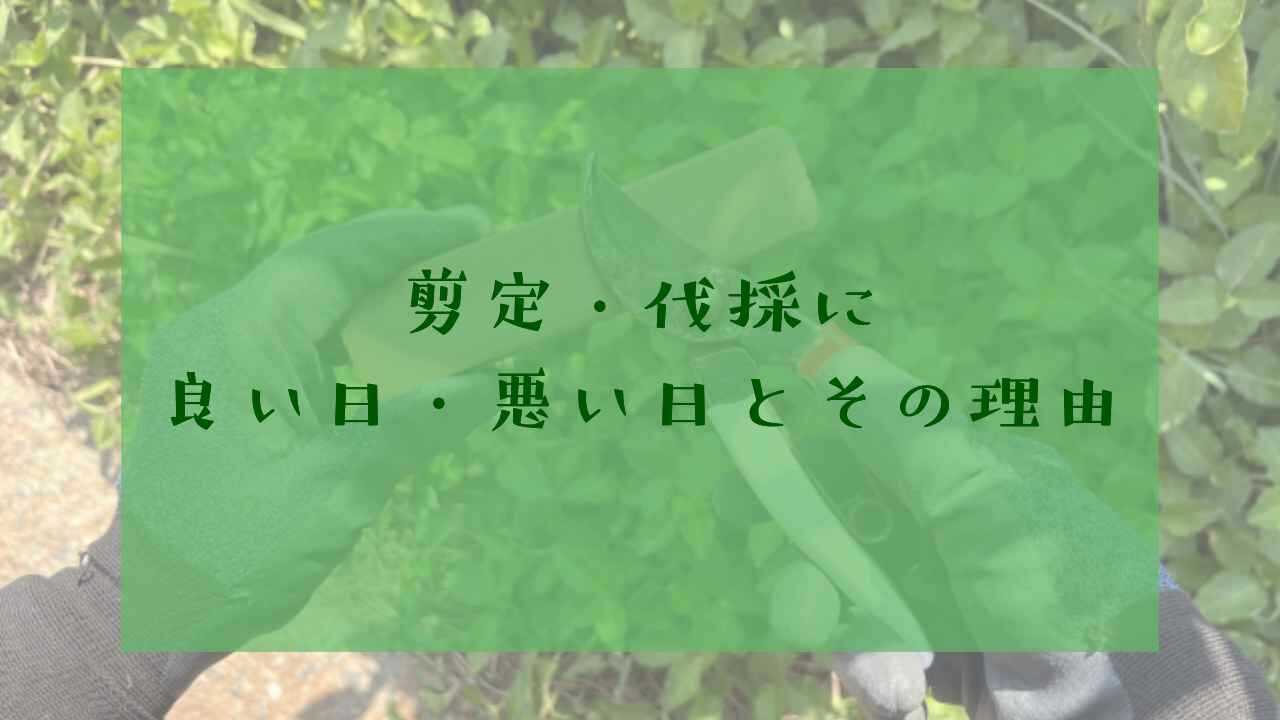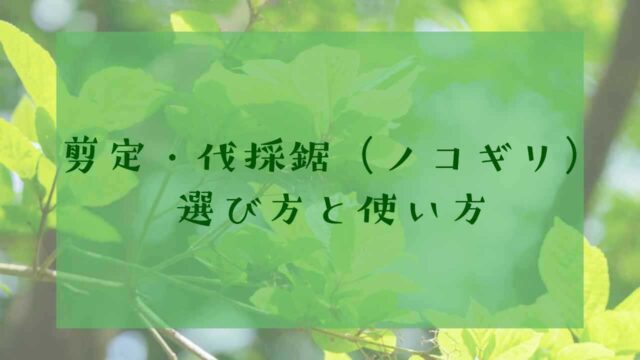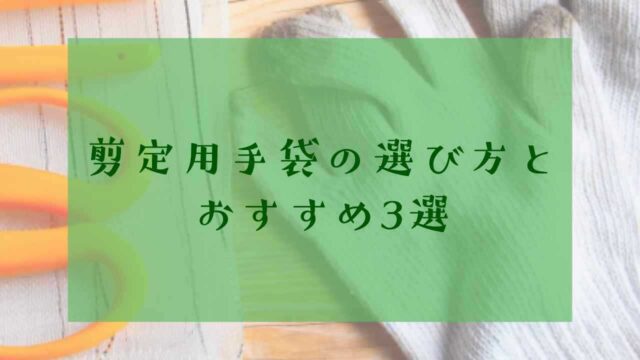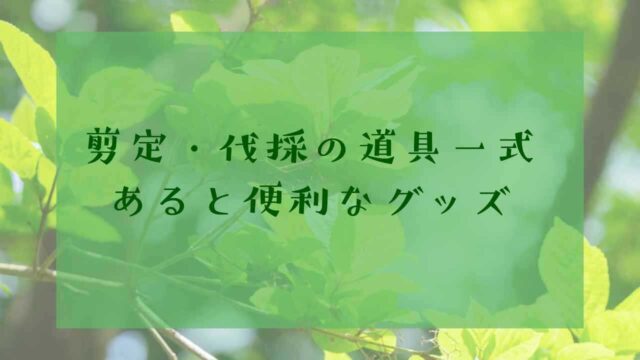庭木の剪定は、いつ切るかによって
木の状態が大きく変わることがあります。
「剪定してはいけない日があると聞いて不安」
「このタイミングで切って大丈夫なのか迷っている」
そんな悩みを持つ人も多いようです。
特に庭植えの木や成長した庭木は、
剪定の判断を誤ると
回復に時間がかかったり、
思わぬトラブルにつながることもあります。
この記事では、
剪定を避けた方がよい時期やタイミングと、
自分で判断しきれない場合の考え方を
分かりやすく整理して解説します。
伸びすぎた庭木を自分で剪定・伐採するのはちょっと不安・・・
という方はプロにお願いするのもおすすめです。
暦上で剪定・伐採を避けるべき日と適した日
剪定には、木にとって負担が大きくなる避けた方がよい時期やタイミングがあります。
この時期に無理な剪定を行うと、枝枯れや樹勢の低下につながることもあります。
・真夏や真冬など、木に強いストレスがかかる時期
・芽吹き直前で養分を多く使っているタイミング
・病害虫が発生しやすい時期
・雨が続き、切り口が乾きにくい状態
こうした条件が重なると、
剪定そのものがリスクになる場合もあります。
木を切ってはいけない日
日本では古くから暦や自然のサイクルに基づいて庭木の手入れを行ってきました。その中でも「大つち・小つち」や「土用」の期間は、木を切ってはいけない日とされています。
大つち・小つちとは?
「大つち」「小つち」の“つち”は「犯土(ぼんど)」とも書かれ、土を犯してはならない期間を意味します。これは陰陽道の考えに基づき、土公神(どくしん)という神様が地中に宿る時期とされているためです。
この期間中は、以下のような土を動かす行為が禁忌とされます。
- 土を掘る・耕す
- 建物の基礎工事
- 井戸掘り
- 墓地への埋葬
- 木の伐採・剪定
林業の現場では、この期間に伐採すると虫が入りやすい、腐りやすいなどの理由から今も避けられることがあります。
大つち・小つちの日にち(2025年)
| 大つち期間 | 小つち期間 |
|---|---|
| 1/1(水)〜1/7(火) | 1/9(木)〜1/15(水) |
| 3/2(日)〜3/8(土) | 3/10(月)〜3/16(日) |
| 5/1(木)〜5/7(水) | 5/9(金)〜5/15(木) |
| 6/30(月)〜7/6(日) | 7/8(火)〜7/14(月) |
| 8/29(金)〜9/4(木) | 9/6(土)〜9/12(金) |
| 10/28(火)〜11/3(月) | 11/5(水)〜11/11(火) |
| 12/27(土)〜1/2(令和8年) | 1/4〜1/10(令和8年) |
土用とは?
「土用」もまた、土公神が地上に現れる期間とされ、土を動かす行為や新しいことを始めるのを避けるべき時期と考えられています。
2025年の土用期間
| 土用区分 | 期間 |
|---|---|
| 冬の土用 | 1月17日(金)〜2月2日(日) |
| 春の土用 | 4月17日(木)〜5月4日(日) |
| 夏の土用 | 7月19日(土)〜8月6日(水) |
| 秋の土用 | 10月20日(月)〜11月6日(木) |
暦や言い伝えで「今日は切らない方がいい」とされる日もありますが、
本当に避けたいのは“樹の弱る切り方・時期”です。
自宅の樹種・樹齢・日当たりなどで最適なタイミングは変わるため、
一度プロに“今切って良いか”を確認してから作業すると失敗しにくくなります。
木を切るのに良い日
逆に、縁起の良い日もあります。
「二十八宿」のひとつ柳宿(りゅうしゅく)は、一般的には凶日とされがちですが、伐採や剪定には良い日とされ、市販の暦や立木伐採カレンダーでも確認可能です。
雨上がりの剪定・伐採はNG?
雨上がりを避けるべき理由
雨上がりの剪定・伐採は避けるのが基本で、主な理由は以下のとおりです。
病気の感染リスクが高まる
剪定のタイミングが悪く、湿気の多い日や雨上がり直後に枝を切ると、切り口から病原菌(主にカビや細菌)が侵入するリスクが高まります。
とくにうどんこ病・黒星病・褐斑病などのカビ系の病気は、湿った環境を好み、傷口から入り込みやすい性質があります。
切り口が乾きにくい
剪定でできた切り口は、木にとっては傷口であり、通常であれば、乾燥とともに自然にふさがり、自己治癒(癒合)しますが、湿度が高いとこの乾燥が進まず、切り口が長時間開いたままの状態になります。
乾きが遅れると、菌が侵入しやすくなるだけでなく、木の回復そのものも遅れてしまい、枝先が枯れ込んだり、次年度の花芽や新芽の生育に悪影響を与える可能性があり、特に太い枝を剪定した場合はこの影響が大きくなります。
樹液の流出
雨の日に剪定を行うと、切り口からの樹液の流出が増加しやすく、植物に大きな負担をかける可能性があり、特に春〜夏の成長期は、枝の中を水分や栄養を含んだ樹液が活発に流れているため、切った瞬間に樹液がにじみ出やすい状態です。
ここに雨が加わると、湿度と水分によって切り口の乾燥が妨げられ、樹液の流出が止まりにくくなり、植物にとって大きなストレスとなります。
それでも剪定が必要なケース
どうしても剪定が必要な場合もあります。
- 台風や大雨で枝が折れた場合
- 害虫や病気が発生している場合
- 緊急で樹形を整える必要がある場合
雨上がりの剪定の注意点
- 天候の回復を待ち、できるだけ乾燥した状態で行う
- 道具の消毒(殺菌)を徹底する
- 切り口に癒合剤や殺菌剤を塗布する
- 剪定後も植物の様子をよく観察する
この剪定は自分でやっていい?判断ポイント
剪定・伐採は晴れて風のない日中がベスト
1日の間でいうと、剪定作業は日没から日の出までに行うのがよいとされていますが、その理由は以下の通りです。
- 植物の活動が鈍る時間帯
夜間は植物の代謝が落ち、樹液の流れや自己治癒力も低下するため、切断によるダメージが大きくなります - 害虫が活動しやすい
夜は害虫の活動が活発になるため、切り口から侵入するリスクが増します - 作業中の事故リスクが高い
視界が悪く、怪我や誤操作の可能性が高くなります
仕事をしているとベストなタイミングで自分で剪定・伐採作業ができないこともあるので、思い切ってプロに任せたいという方はこちらも参考にしてみてくださいね。
剪定110番ならご都合のいい日に合わせて全国どこでも
安心して任せられるプロにお願いできます。
剪定・伐採にお祓い・お清めは必要?
必ずしも必要ではありませんが…
日本には「八百万の神(やおよろずのかみ)」という考え方があり、自然界のすべてに神が宿るとされます。長年そこにあった木には、土地を守る「守り神」のような存在として感謝の気持ちを持つ方も多いです。
特に神社にある御神木は伐採がタブーとされるほど神聖なもので、一般家庭の庭木であっても長年その土地に根付いた木は、家や住む人々にとって守り神として敬われていることもあります。
しかし枯れてしまったりその他諸々の理由で上記のような木を伐採せざるを得ないこともあり、そのような時はお祓いやお清めを行うことで悪い影響を少なくし、安心して伐採できると考えられています。
自分でできる簡単なお祓い方法
神社や寺院に依頼せずとも、自分でも簡単なお清めの儀式を行うことができ、日本酒と塩を用いて以下のように行うのが一般的な手順です。
- 伐採する木の前に立ち、深呼吸して心を落ち着けます。
- 木に向かって、感謝と謝罪の気持ちを心の中で丁寧に伝えます。
- 塩を木の根元や周囲に少量ずつ撒きます。
- 日本酒も同様に、木の根元や周囲に少量ずつ撒きます。
神社や寺院に依頼する本格的なお祓い
より丁寧な儀式を希望する場合や、樹齢の高い木、代々守られてきた木などを伐採する際は、神社や寺院にお祓いを依頼してもよいでしょう。
依頼の流れと費用の目安
- まずは連絡
近隣の神社や寺に連絡し、伐採の理由や木の種類・大きさ・場所などを伝える - 費用の相場
一般的には初穂料や御祈祷料として5,000円〜30,000円程度を支払う - お供え物
お米・お酒・塩などのお供え物を用意する必要がある場合もある
まとめ
この記事では、剪定・伐採を行う上で気をつけるべき暦上の良い日・悪い日、雨上がりの注意点、お祓いやお清めの意味と方法について解説しました。
剪定は、「正しい日を知ること」だけでなく、
「無理をしないこと」も大切です。
不安を感じながら作業を進めるよりも、
一度立ち止まって判断を整理することで、
庭木も人も傷つかずに済みます。
自分でできる剪定と、
判断が難しい剪定を分けて考えることが、
失敗を防ぐ一番の近道です。
- 暦上の「大つち・小つち・土用」の期間は避けるのが無難
- 雨上がりの剪定は病気や弱りの原因になるため基本はNG
- 剪定は晴れた風のない日中に行うのが理想
天候や植物の状態だけでなく、心や気持ちも整えて剪定・伐採を行うことで、より安心かつ丁寧な庭づくりにつながるので、ぜひ参考にしてみてください。