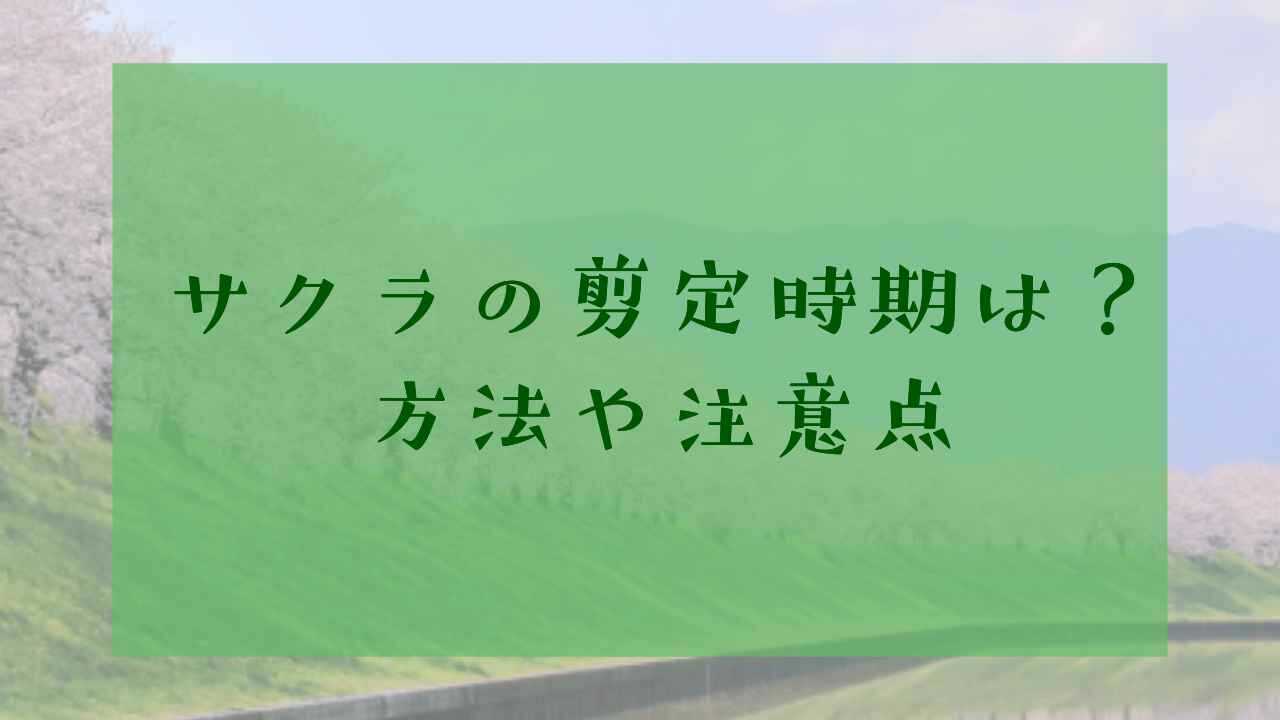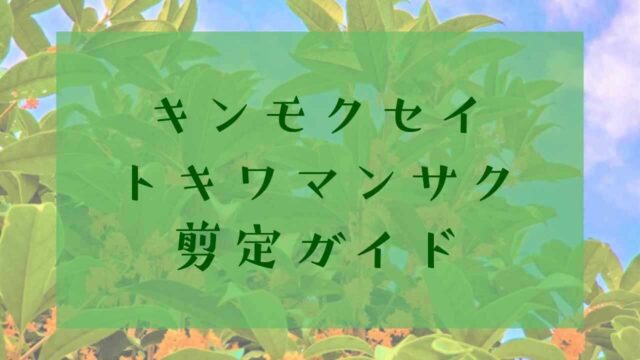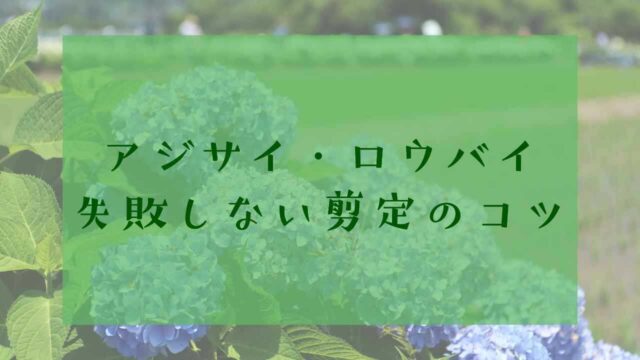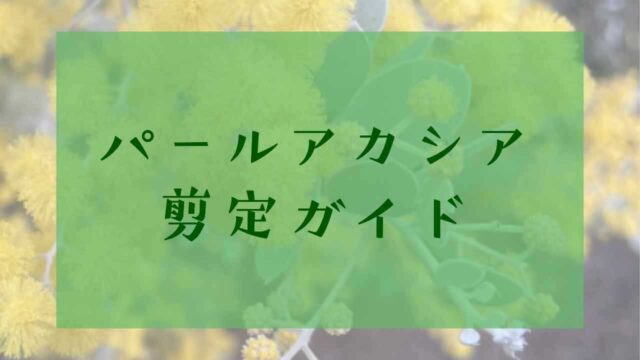桜は春の訪れを告げる象徴ですが、その美しい姿を維持しながら毎年豊かな花を咲かせるためには、適切な手入れが不可欠です。
本記事では、桜の剪定の正しい時期、適切な方法、さらには品種別ケアを解説します。
花木の剪定時期一覧表はこちらの記事をどうぞ!
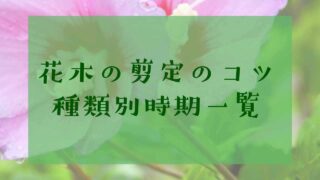
サクラ(桜)の剪定について

桜の剪定は休眠期が鉄則
桜の剪定に最適なのは樹木が活動を停止している休眠期で、具体的には落葉後の11月~2月頃は、樹液の動きが穏やかなため、剪定による木への負担を最小限に抑えられます。
特に、12月は剪定の適期とされ、遅くとも2月までには作業を終えることが望ましいとされていますが、これは桜が比較的早く樹液の活動を開始するため、春の本格的な生長が始まる前に剪定を完了させる必要があるからです。
桜は切り口から水分が染み出しやすく、乾燥しにくいという特性上、切り口にカルスと呼ばれる傷口を塞ぐ組織が形成されにくく、病原菌が侵入しやすい状態が長く続きます。
休眠期に剪定を行うと樹液の流出が少なくなり、切り口が乾きやすく、病原菌が侵入する機会を減らし、樹木が傷口を癒合させるための準備期間を確保できるのです。
時期を誤るとどうなる?剪定時期ごとのリスク
桜の剪定は、最適な時期以外に行うと、樹木に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。
春~夏(生長期)の剪定を避けるべき理由
春から夏にかけての生長期は桜の樹液が最も活発に流れる時期なので、この時期に剪定を行うと、切り口から大量の樹液が流出し傷口がなかなか乾きません。
湿った状態が長く続く切り口から病原菌(特に「胴枯れ病」の原因菌)が繁殖し、樹木内部に侵入する温床となり、さらに生長期の強剪定は樹勢を著しく弱めてしまいます。
樹液の流れが活発な時期の剪定は、単に花が減るだけでなく、樹木の生命力そのものを奪いかねない行為であることを理解しておく必要があります。
厳寒期の剪定を避ける理由
冬の休眠期が最適であるとはいえ、極端に気温が低い厳寒期の剪定も、切り口の組織が凍結や乾燥によって傷み、傷んだ組織は癒合が遅れ、結果的に病原菌の侵入リスクを高める可能性があります。
目的別剪定の種類
剪定は、その目的と規模によって大きく二つに分けられます。
基本剪定(冬)
冬の休眠期に行われる剪定で、不要な大枝の除去や、将来の樹形を形成するための骨格作りが主な目的で、この時期に行うと樹木への負担を最小限に抑えられます。
桜を傷めない正しい剪定方法
桜の木を剪定する際には、切り口の処理が非常に重要で、適切な切り方をすることで傷口を速やかに癒合させ、病原菌の侵入を防ぐことができます。
ブランチカラーを残して切る
桜の剪定において最も重要な原則の一つが、枝の付け根にあるブランチカラー(枝隆)と呼ばれる、幹と枝の境界にあるわずかな膨らみを残して切ることです。
ここには、樹木が自ら傷口を塞ぐための防御層と呼ばれる特殊な組織が存在し、この防御層は、病原菌の侵入を防ぎ、傷口を覆うカルスを速やかに形成する役割を担っているので、その外側で切断するのが正しい方法です。
剪定道具の消毒を忘れずに
剪定作業を始める前には、使用するハサミやノコギリの刃の部分をアルコールなどで消毒することで、病原菌が剪定道具を介して他の枝や樹木全体に広がるのを防ぎ、健康な樹木への感染リスクを抑えられます。
しだれ桜・盆栽桜の剪定について
桜には、ソメイヨシノ、ヤマザクラ、オオシマザクラ、エドヒガン、カンヒザクラなど、多種多様な品種が存在し、それぞれ成長の仕方、樹形、枝の伸び方などが異なります。
剪定の基本的な原則は共通するものの、樹形を保ち、その品種特有の美しさを引き出すためのアプローチは、それぞれの特性に合わせて調整する必要があります。
しだれ桜

しだれ桜は、その名の通り枝が優雅に垂れ下がる姿が特徴的で、この独特の樹形を美しく保つには、特別な剪定のコツと注意点があります。
しだれ桜特有の注意点
しだれ桜の垂れ下がった枝は、地面に触れてしまうと、そこから病原菌が侵入したり、枝が腐ったりする原因となるため注意が必要で、枝が過度に密集すると内部の枝が枯れ込みやすくなるため、適度に間引きましょう。
剪定のコツ
しだれ桜の剪定は、単に不要な枝を取り除く作業に留まらず、その品種特有の美しさを引き出し、維持するための造形の側面が強くあります。
幹に近い部分に空間を作り、樹形を乱す上向きに伸びる立ち枝や、幹から直接生える胴吹き枝を付け根から切り落としていきますが、イメージとしては、外側に伸びる枝は残し、下に垂れる枝の中で過度に密集しているものを間引くと良いでしょう。
- 誘引
支柱などを使って木の中心部分を真っ直ぐ上に成長させることで全体のバランスを整える技術で、適切に誘引すると樹冠全体にまんべんなく日が当たり、成長した枝が地面につきにくくなって病気や害虫の予防にもなります。 - 芯止め
しだれ桜が望む高さまで成長した頃に、頂点部分を切る芯止めをすると上に伸びるのを抑制し、横方向に枝や葉が増えていくのを促すのでより豊かな樹冠を形成できます。
桜の剪定は、枝を切る作業そのものだけでなく、その後のケアが樹木の健康を左右するので特に切り口からの病原菌侵入を防ぐことが重要です。
切り口は癒合剤でケア
前述の通り、桜は切り口から腐りやすく、病原菌が侵入しやすいという特性を持っているので、剪定後には必ず癒合剤を塗布しましょう。
癒合剤は、剪定した切り口を保護するもので病原菌(特に胴枯れ病菌など)の感染リスクを大幅に低減し、樹木が自ら傷口を塞ぐカルスの形成も促進できます。
病害虫対策と年間管理
桜の健康を維持するには、年間を通じた病害虫対策と適切な管理が不可欠です。
定期的な観察と早期発見を
春から秋にかけての生長期には、定期的に桜の木を観察し、枝や葉の裏に虫がついていないか、病気の兆候がないかを確認し、早期に異常を発見できれば、被害が広がる前に適切な対策ができます。
- 胴枯れ病
最も多い病気の一つで、幹や枝に病斑ができ、進行するとその部分から上が枯れます。冬期に罹病枝を切除することが効果的とされています - ナラタケ病
根の腐朽を引き起こし、最終的に枯死に至らせることがあります。
毛虫対策
桜は強い剪定により花付きに大きな影響が出る可能性があるため、毛虫の害を避ける目的だけで強い剪定を行うことはお勧めできないので、農薬の散布など他の方法で対処することが望ましいでしょう。
まとめ
本記事では桜の剪定の正しい時期と方法、品種別ケアと年間管理について解説しました。
- 剪定の最適な時期は桜の休眠期である11月頃から2月頃まで
- 剪定時は枝の付け根にあるブランチカラーを残して切る
- 桜は切り口から病原菌が侵入しやすいので、剪定後には必ず癒合剤を塗布する
この記事が美しい桜の維持に役立てば幸いです!