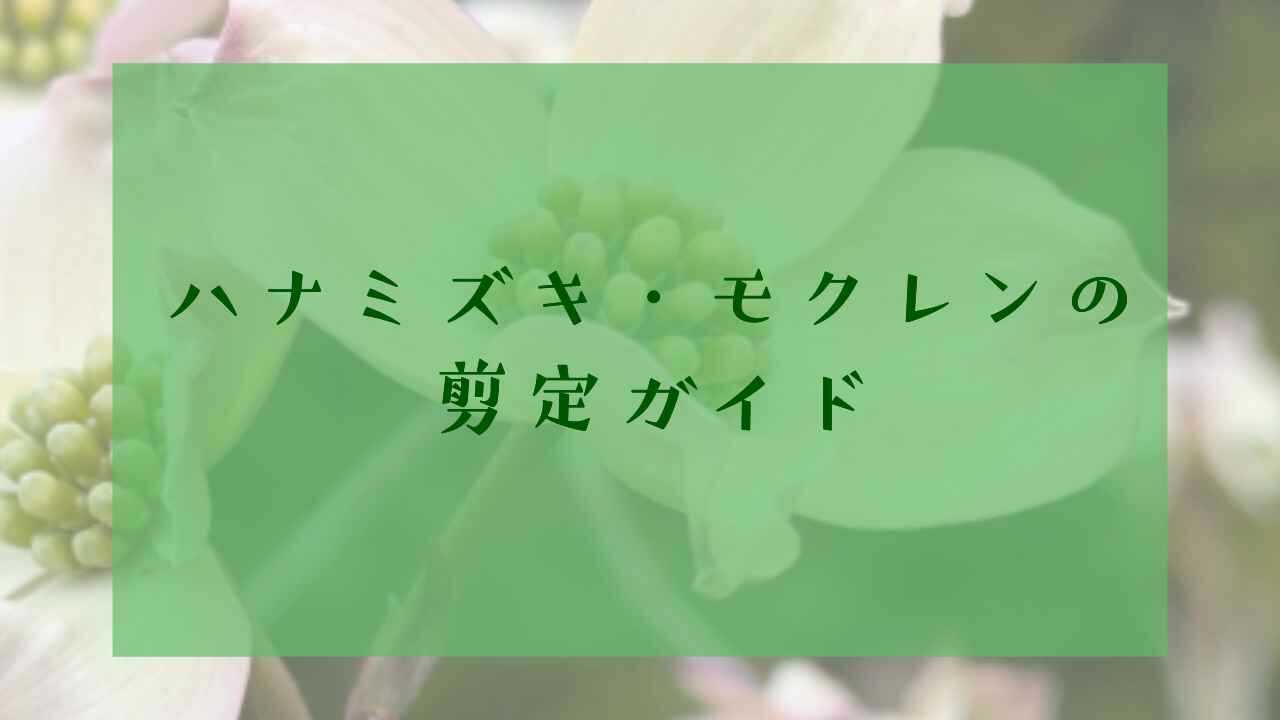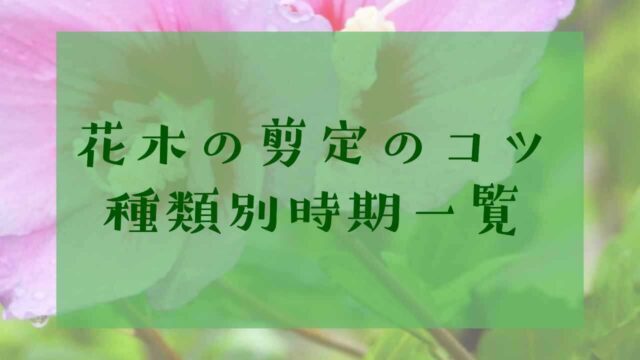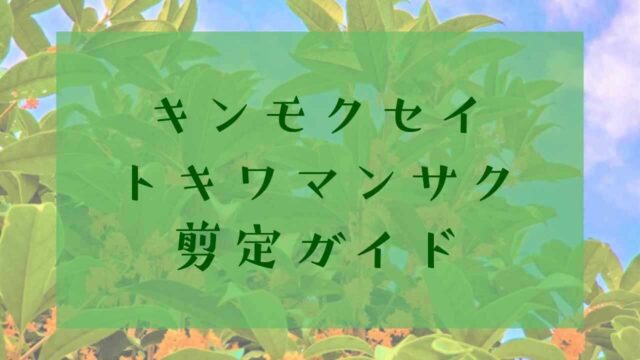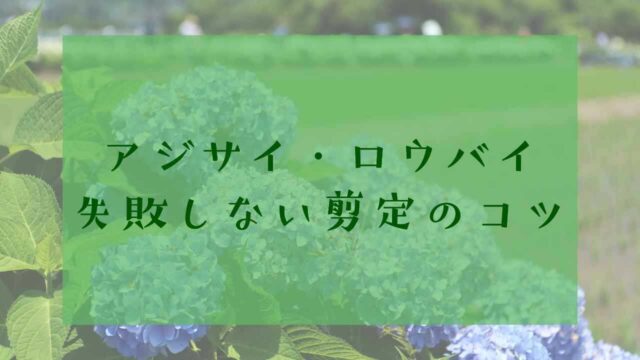ハナミズキはアメリカヤマボウシとも呼ばれ、シンボルツリーとして人気で、秋には赤い実をつけることでも知られる一方、モクレンは春先に天に向かって咲く高貴で上品な花が魅力であり、両者ともに適切な剪定を行うことで、その魅力を最大限に引き出すことができます。
この記事では、ハナミズキとモクレンに最適な剪定時期と方法、知っておくべき注意点まで詳しく解説します。
花木の剪定時期一覧表はこちらの記事をどうぞ!
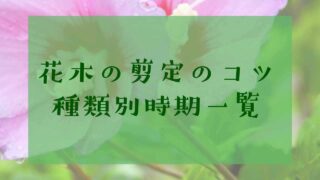
ハナミズキの剪定
ハナミズキは、比較的自然に樹形が整いやすい落葉樹であり、頻繁な強剪定はあまり必要ありませんが、放置すると大きくなりすぎたり、枝が混み合って花付きが悪くなるので適切な剪定を行うと毎年豊かな花を楽しむことができます。
ハナミズキは旧枝咲き

ハナミズキの花は、その年に新しく伸びた枝の先端(頂芽)に6~8月頃から花芽を形成し、翌春にその花芽から花を咲かせる「旧枝咲き」の特性を持つため、花芽を保護し、木へのダメージを最小限に抑える時期を選びましょう。
ハナミズキの最適な剪定時期と理由
基本は休眠期(11月~3月頃)
この時期はハナミズキが休眠に入っており、木への負担が最も少ないため、比較的大きな剪定も行いやすく、葉が落ちているため、枝の全体像や花芽の位置を確認しやすく、不要な枝を正確に見極めて剪定することができます。
ただし、冬に強剪定を行い樹形を大きく仕立て直した場合は2年間開花が見込めない場合があります。
軽い剪定なら花後(5月下旬~6月頃)も可能
花が咲き終わった直後には、軽く不要な枝を間引く「透かし剪定」を行うことができて、この時期の剪定は、風通しと日当たりを良くし、その後の花芽形成を促進する効果が期待できますが、あくまで軽めの剪定に留め、花芽が形成される7月以降の剪定は避けます。
最も剪定を避けるべき時期は花芽形成期(7月~8月以降)
ハナミズキの花芽の形成が始まるこの時期に剪定を行うと、翌年に咲くはずの花芽を誤って切り落としてしまう可能性が非常に高くなるので、夏に枝が伸びて邪魔に感じても、翌年の花を楽しむためには秋まで待ちましょう。
ハナミズキの具体的な剪定方法
ハナミズキの剪定は、その自然な樹形を活かし「柔らかい球体」や「円錐形」を目指して剪定を行うと良いでしょう。
間引き剪定(透かし剪定)が基本
ハナミズキは強剪定に弱い傾向があるため、基本的には枝が混み合った部分を透かすように剪定し、特に幹から勢いよく真上に伸びる徒長枝は花芽をつけにくく、養分を無駄に消費するので根元から切り落とします。
切り戻し剪定を行う場合
大きく広がりすぎた枝や、古くなった枝を短くしたい場合に行い、理想的な長さの短い枝がある分岐点や外側に向かう芽の上で切り戻します。
ハナミズキは横に枝が伸びる性質があり、放っておくと大きく広がりがちなため、適切な位置で切り戻すことで、樹高や幅をコントロールし、コンパクトな樹形を維持できます。
摘蕾(てきらい)のすすめ
ハナミズキは花芽がたくさんつきすぎると、翌年の花付きが悪くなる隔年開花の性質を持つことがあるので、毎年安定して花を咲かせたい場合は、花芽が多すぎる年に一部の花芽を摘み取る摘蕾を行うと良いでしょう。
ハナミズキの剪定の失敗例とケア
剪定後の適切なケアは、ハナミズキの健康と回復を左右します。
花が咲かない主な原因
- 花芽形成期(7~8月以降)に剪定し、翌年の花芽を切り落とした
- 日照不足による花芽の生育不良
- 肥料不足
- 隔年開花による花数の減少
癒合剤の重要性
特に太い枝を剪定した際は、切り口の治りが遅く、傷口から病原菌(腐朽菌など)が侵入しやすくなるので、癒合剤を塗布することで切り口を保護し、水や養分の流出を防ぎ、傷口の回復を早める効果があります。
モクレンの剪定
モクレンは、春の訪れを告げるように天に向かって咲く大きな花が魅力的な樹木ですが、成長が早く、放置すると大きくなりすぎる傾向があるので、剪定で樹形をコントロールすることが重要です。
モクレンの最適な剪定時期とその理由

ハナミズキと同様、モクレンの花芽は夏頃に枝先に形成され、それが一年かけて成長し、翌年の花となるので、この花芽を誤って切らないように時期と方法に注意が必要です。
花後すぐ(4~5月頃)が理想的
花が散った直後、できる限り早めに剪定を行うのが最もおすすめで、この時期であれば翌年の花芽がまだ形成されていないか、あるいは形成前の状態であるため、誤って花芽を切り落とすリスクを最小限に抑えられます。
遅れると夏にかけて新たな花芽形成が始まってしまうため、注意が必要です。
冬期(1~2月頃)も可能だが注意が必要
葉が落ちて休眠状態に入る冬期も剪定に適した時期とされ、この時期は花芽と葉芽の見分けがつきやすい(花芽は膨らみが大きく、葉芽は長細くて小さい)ため、花芽を避けて不要な枝のみを切り落とすことが可能です。
ただし冬は傷が癒合しにくい傾向があるので、不必要な強剪定は避けるべきです。
モクレンの具体的な剪定方法
モクレンは成長速度が速いため、定期的な剪定で樹高や樹形をコントロールしましょう。
軽めの透かし剪定が基本
モクレンは強い切り戻しにはあまり強くないため、基本的には混み合った枝を整理し、不要枝を根元から間引く「透かし剪定」を行うことで、花付きも維持しやすくなります。
特に、花芽をつけない真上に伸びる徒長枝や、長く伸びた枝は根元から切り落とすのが理想的で、途中で切るとそこからさらに枝が密生してしまうことがあります。
樹高の調整と樹形形成
モクレンは放置すると非常に大きくなるため、住宅地の庭などでは適度な大きさに保つための調整が必要で、樹高を抑えたい場合は剪定の際に下向きの枝をいくつか残すようにすると良いでしょう。
木が適当な高さまで伸びた頃に、頂点部分を切る「芯止め」を行うことで、それ以上の高さを抑え、横方向への枝の広がりを促すことができます。
モクレンの剪定の失敗例とケア
モクレンもハナミズキと同様に、剪定後のケアが重要で、癒合剤と花後のお礼肥(4~5月頃)と冬の寒肥(1~2月頃)が推奨されます。
花が咲かない主な原因
- 剪定時期の間違い
- 品種の問題
- 鳥による蕾の食害
癒合剤(ゆごうざい)の重要性
モクレンも切り口が腐りやすく、病原菌が侵入しやすい樹木であり、特に太い枝を切った場合は、切り口の治りが遅く、傷口から病気が入りやすくなるため、「トップジンMペースト」や「カルスメイト」などの癒合剤の塗布が強く推奨されます。
肥料と水やり
剪定は樹木の健康を保つ上で不可欠ですが、それだけで十分ではありません。適切な肥料と水やりも、豊かな花付きと健全な成長には欠かせない要素です。
お礼肥(おれいごえ)
花が咲き終わった後(ハナミズキは5~6月頃、モクレンは4~5月頃)に与える肥料で、花を咲かせて疲労した木の体力を回復させる目的があります
寒肥(かんごえ)
冬期(ハナミズキは冬、モクレンは1~2月頃)に与える肥料で、春の芽出しと根の成長を助け、翌年の花付きの準備をします
病害虫対策について
枝が密集した状態は、風通しや日当たりを悪くし、病原菌や害虫にとって好ましい環境を作り出すので、剪定は病害虫の予防と対策において非常に重要な役割を担います。
病気:うどんこ病(葉に白い粉状のカビが付着)、斑点病(葉に褐色の斑点)、白紋羽病(根や地際部の樹皮に白い菌糸束)など。
害虫:風通しが悪いとアブラムシなどの吸汁性害虫が発生しやすくなります。
モクレンの主な病害虫
病気:うどんこ病、黒星病(葉に黒い斑点)、すすかび病(アブラムシの排泄物(蜜露)を栄養源とする黒いカビ)など。
害虫:カミキリムシ、アブラムシ、ケムシ(アオムシ)など、アブラムシはすすかび病の原因にもなります。
ハナミズキ・モクレンの剪定|まとめ
ハナミズキとモクレンの剪定とケアについて本記事ではお伝えしました。
- ハナミズキは旧枝咲きなので7月以降の剪定は避け、休眠期の冬に透かし剪定を
- モクレンは花後剪定が最も理想的、冬期の剪定は花芽を見極めて慎重に
- 剪定の際は正しい切り方で行い、切り口には必ず癒合剤を塗布しましょう
この記事が、あなたの庭のハナミズキとモクレンの手入れの際に、お役に立てば幸いです!