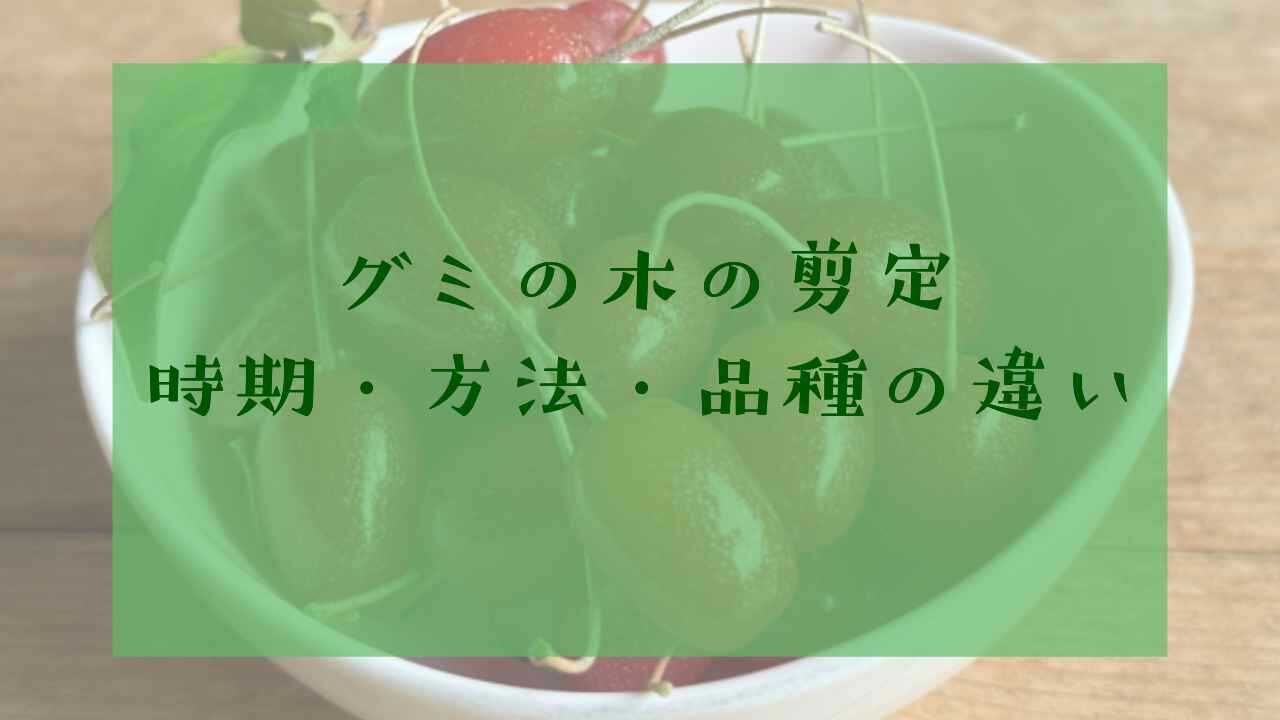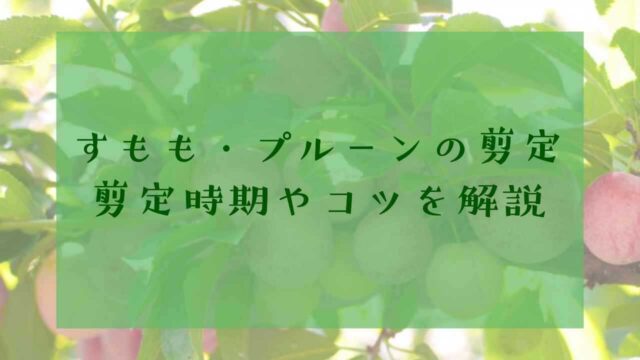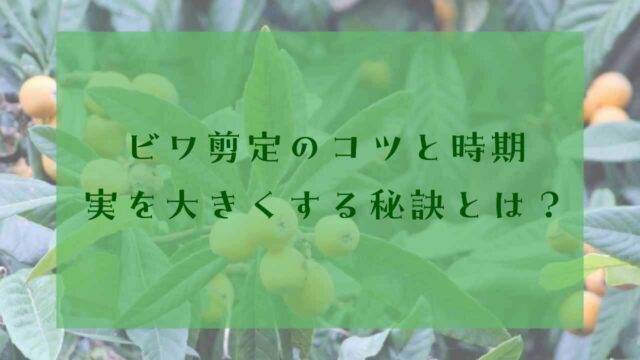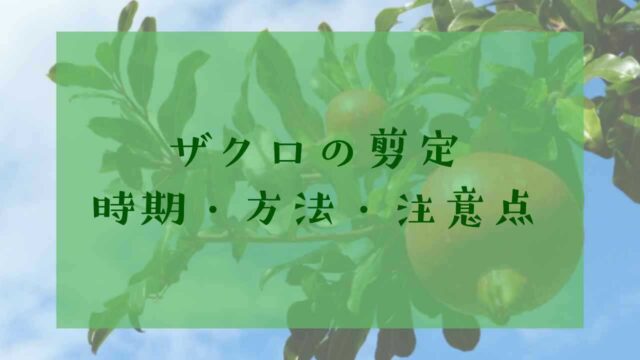グミ(茱萸)は、日本をはじめアジアに広く自生する落葉性または常緑性の低木で、赤く小さな実はジャムや果実酒としても活用できます。
こちらの記事ではグミの品種、剪定方法、育て方について解説します。
グミ(茱萸)について

グミの木は以下のような理由で家庭用果樹として人気があります。
- 丈夫で育てやすい:乾燥や病害虫に強く、初心者にも扱いやすい
- コンパクトなサイズ:大きくなりにくく、庭植え・鉢植えの両方に適している
- 美しい葉と実:春〜初夏に白い花が咲き、初夏~秋には実を楽しめる
特に果実は赤色や橙色に熟し、渋味と甘味のバランスが特徴的で、完熟すると甘味が強くなり生食も可能です。
渋みが強い品種はジャム・果実酒・ゼリー・乾燥果実などに加工され、栄養上も実にはビタミンC、リコピン、ポリフェノールなどが含まれており、抗酸化作用も期待されています。
北海道南部以南で栽培可能で耐寒性があり、乾燥にも耐えうる耐暑性もありながら、さらに痩せた土地でもよく育つという特性があります。
育て方の基本は、日当たりの良い場所を選んで水はけの良い土に植え、根付くまでは乾燥に注意し、剪定と合わせて、年1回の施肥(2月〜3月)も行いましょう。
グミの代表的な品種
ナツグミ(夏茱萸)
- 特徴:春に花が咲き、6月ごろに果実が赤く熟す
- 果実:やや酸味があり生食やジャムに
- 用途:食用・庭木・生け垣
アキグミ(秋茱萸)
- 特徴:ナツグミよりも開花・結実が遅く、秋に赤い実をつける
- 果実:渋みが強く、熟すと甘味が出る
- 用途:主に観賞用(実は鳥の好物)
ダイオウグミ(大王茱萸)
- 特徴:果実が非常に大きく、生食でも甘みがあり美味しい
- 果実:赤くて大粒、ジャムや果実酒向き
- 用途:食用に最適、家庭果樹として人気
ビックリグミ(太陽グミ)
- 特徴:品種改良された大型果実種
- 果実:直径2~3cmの赤い実、酸味と甘みのバランスが良い
- 用途:食用(生食・加工)・育てやすい品種
マルバグミ(丸葉茱萸)
- 特徴:葉が丸く常緑性で、秋~冬に実をつける
- 用途:観賞用や生け垣向け。果実は小さくあまり食用向きでない
- 耐陰性・耐潮性:高く、海辺の植栽にも使われる
品種選びのフローチャート(家庭果樹向け)
Q1:主に食用として楽しみたいですか?
YES → Q2へ
NO(観賞目的)→「マルバグミ」がおすすめ(常緑・葉が美しい)
Q2:生食メイン?ジャムや加工もしたい?
生食メイン→「ダイオウグミ」または「ビックリグミ」
加工が中心→「ナツグミ」または「アキグミ」
Q3:収穫時期は夏と秋、どちらがいい?
夏(6月)→ 「ナツグミ」
秋(10月前後)→「アキグミ」または「マルバグミ」
Q4:庭植え?鉢植え?
鉢植えにしたい→「ビックリグミ」「ナツグミ」が適している(コンパクト)
庭植えOK→全品種対象可(育てやすさ優先)
グミの剪定について
剪定の必要性について
グミの木にとって剪定は、樹形を整えるだけでなく、果実の収穫量や健康維持にも直結する大切な作業であり、放置すると枝が混み合って風通しが悪くなることで病害虫の温床にもなりかねません。
剪定は冬剪定と夏剪定の2回が基本
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 冬剪定(12月〜2月) | 落葉期に行う基本の剪定。大きな枝の整理と樹形作り |
| 夏剪定(7月〜8月) | 果実収穫後に軽く整枝し、徒長枝や混み合った枝を間引く |
実をたくさんつけるための剪定方法

グミの木で実を豊作にするには、不要な枝を取り除き、結果枝を伸ばすことが重要なので以下のような剪定方法を意識するようにしましょう。
- 間引き剪定:内向き・下向き枝、交差する枝、混み合った枝は基部から切除
- 切り返し剪定:伸びすぎた枝は、2〜3節残してカットすると次年度再生する
- 花芽を意識:花芽のついた枝は、できるだけ残しましょう。
グミは自然樹形を活かした軽い剪定が基本で、剪定のやりすぎは逆効果になるので、年々様子を見ながら調整していきましょう。
特に剪定する際は、新しい枝の中ほど〜先端をなるべく残し、花芽のついた枝は極力残すことを意識するのが豊作のコツです。
実がならない原因と対処法
グミの木が育っても実をつけない場合、以下の点をチェックしましょう。
剪定しすぎて花芽がない
前年に伸びた枝の先端に花芽がつくので、剪定は軽めに、花芽のついた枝は残して間引き剪定を行いましょう。
受粉がうまくいっていない(単独品種)
異なる品種を近くに植えると実つきが良くなります。
日照不足
グミは日照時間が短い場所では実つきが悪くなるので、南向きに移植するのも有効です。
肥料過多(特に窒素分)
葉ばかり茂り、花芽がつきにくくなるので、肥料は控えめに、春と秋にバランス型を施肥しましょう。
剪定後のケア
剪定後もしっかりと管理すると、グミの木は元気に育つことができるので、ここでは具体的なケアのポイントを紹介します。
切り口の保護
太めの枝を切った場合は癒合剤(トップジンMペーストなど)で切り口を保護し、雑菌の侵入を防ぎましょう。
水やりの調整
剪定直後は水の吸収力が落ちるため、過湿を避けて土の表面が乾いたら水やりを。
害虫・病気対策
グミの木は比較的丈夫ですが、放置すると病害虫が発生することもあるので、日当たり・風通しの確保と、清潔な環境の維持で予防しましょう。
主な害虫と対処法
| 害虫名 | 症状 | 対策 |
|---|---|---|
| アブラムシ | 若葉や新芽に群がり、汁を吸って葉が巻く | 発見次第、水で洗い流す。多発する場合は殺虫剤(ベニカ系)を使用 |
| カイガラムシ | 茎や葉に白い小さな塊。成長を妨げる | 歯ブラシや綿棒でこすり落とす。越冬期にマシン油乳剤を散布 |
| コガネムシの幼虫 | 根を食べて生育が悪化、枯死の原因に | 鉢植えは土の入れ替え時にチェック。発生時はスミチオン粒剤等で駆除 |
主な病気と対処法
| 病名 | 症状 | 対策 |
|---|---|---|
| うどんこ病 | 葉の表面に白い粉。光合成が妨げられる | 発生初期にベニカファインスプレーなどの殺菌剤を使用 |
| 灰色かび病 | 花や実、葉が褐色に変色し、カビが広がる | 通風・日照を確保し、混み合った枝を剪定することで予防 |
勢いに任せて一気に剪定すると、木にストレスがかかり、回復に時間がかかることもあるため、剪定は段階的に、様子を見ながら少しずつ行いましょう。
グミの剪定|まとめ
本記事ではグミの剪定について詳しく解説しました。
- 剪定は主に2〜3月に整枝し、必要に応じて夏にも軽剪定を行いましょう
- 実をたくさんつけたいなら、花芽のついた枝を意識的に残す間引き剪定を
- 剪定はやり過ぎず、癒合剤・水やりの調整などのアフターケアも大切に
グミの剪定は難しくはありませんが、品種特性や成長サイクルを理解するとさらに実り多くなるので、この記事がお役に立てば幸いです。