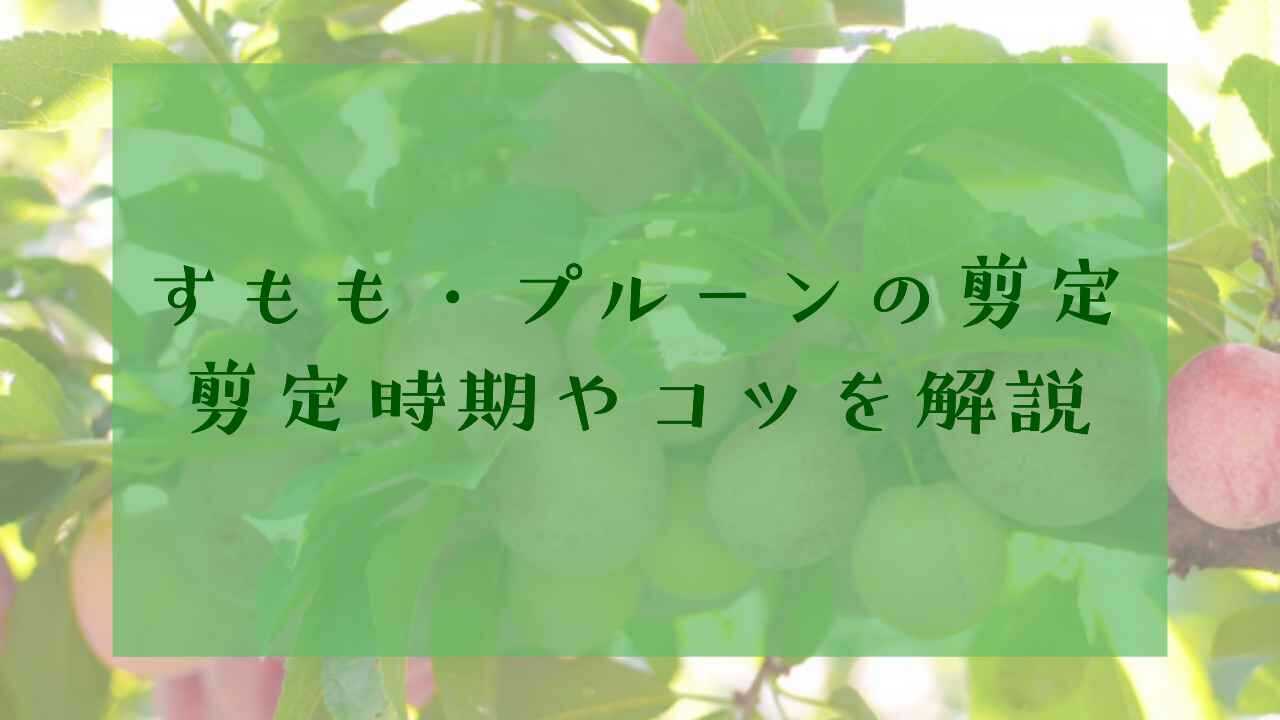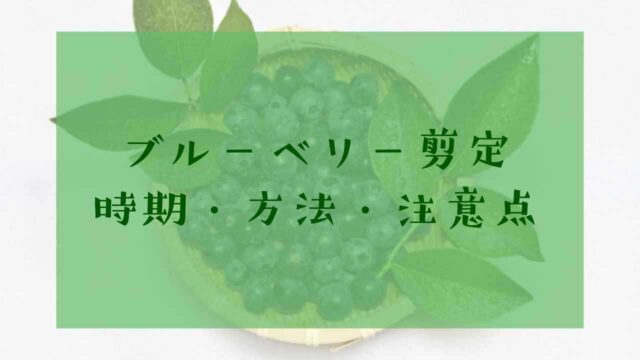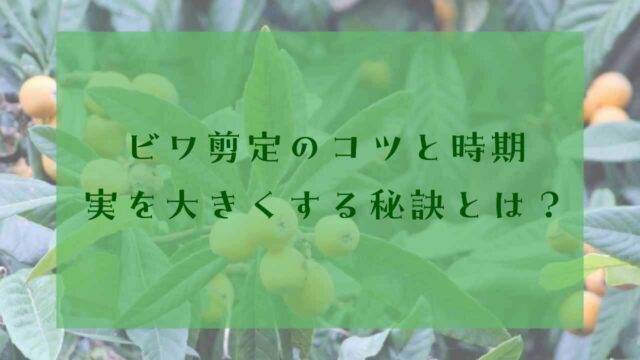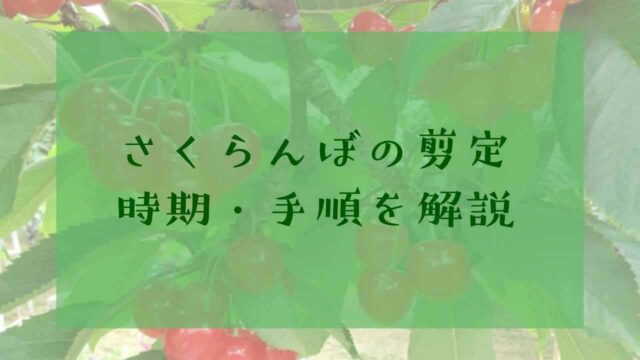この記事では、剪定のタイミングや方法だけでなく、すももとプルーンの違いや品種の特徴、剪定上の注意点まで、初心者向けにわかりやすく解説します。
すもも(李)とプルーンの違いとは?
すもも(Japanese plum)とプルーン(European plum)は、どちらもバラ科サクラ属の果樹で見た目も似ていますが、植物としての特性や果実の用途、剪定方法には違いがあります。
すももについて

- 原産地:中国〜日本
- 果実:ジューシーで香り豊か、生食向き
- 樹形:横に広がる「横張り性」
- 受粉性:自家不結実が多く、複数品種の植栽が必要
主な品種
- 大石早生(おおいしわせ): 極早生種で甘みが強く人気。
- ソルダム: 酸味と甘みのバランスが良い中生種。
- サンタローザ: アメリカ由来で大玉。香りが濃厚。
プルーンについて

- 原産地:ヨーロッパ
- 果実:甘味が強く、乾燥しても栄養価が高いため、ドライフルーツに最適
- 樹形:縦に伸びる「立ち性」
- 受粉性:自家結実性が高く、1本でも実が付きやすい
主な品種
- スタンレイ:世界的に普及。収量が安定している
- シュガープルーン:糖度が非常に高く、生食にも◎
- バーバンク:プルーンとすももの交雑種で、剪定方法はすもも寄り
すもも・プルーンの剪定について
剪定を行う最大の目的は、果樹の健康と果実の品質向上です。
枝が増えすぎると日当たりや風通しが悪化して病害虫が発生しやすくなったり、栄養が枝や葉に分散して、果実が小さくなり実の数も減少してしまいます。
特にすもも・プルーンは枝の生育が旺盛なので、毎年の剪定で樹形を整えると作業性がアップし、翌年の実付きも安定するので欠かせない作業といえるでしょう。
すももとプルーンの剪定の違い
| 特性 | すもも | プルーン |
|---|---|---|
| 樹形 | 横張り性 | 立ち性 |
| 剪定の目的 | 枝の混みを解消 | 樹形維持・整枝中心 |
| 花芽の位置 | 前年枝の側芽 | 同様だがやや品種差あり |
| 剪定量の目安 | 全体の2~3割 | 同程度(実付きが良いため注意) |
すももは枝が混みやすいため「間引き剪定」、プルーンは立ち性を活かし「整枝・誘引」を意識した剪定が効果的です。
すもも・プルーンの剪定時期
剪定は、行う時期によって目的が異なります。以下のようなサイクルを意識しましょう。
冬剪定(1〜2月)
落葉後の休眠期に行う剪定で、主に不要な枝の整理と樹形の調整を行います。
春の軽剪定(3月頃)
芽が動き出す前の調整として冬に切り残した細い枝の除去など軽めに行いますが、この時花芽を切り落とさないように注意が必要です。
夏の摘心(6〜7月)
枝葉が繁茂してきたら、摘心・間引きを軽く行う程度にし、果実の成熟期には強剪定を避けましょう。
- すももは混みやすいので冬にしっかり剪定を
- プルーンは軽めでもOKだが、毎年の形づくりが大切
すもも・プルーン剪定の基本手順
初心者の方でも、以下のステップに沿って剪定すれば安心です。
不要な枝を取り除く
枯れ枝、病気の枝
内側に向いた枝、交差する枝
真上・真下に伸びた徒長枝
主枝・副枝の構成を確認
主枝は果樹の骨格なので、副枝や不要な小枝を整理する
枝の切り方に注意
枝の根元を少し残し、2〜3cm上を斜めにカット
雨の日を避け、晴天時に行うのがベスト
切りすぎに注意
全体の2〜3割以内が基本で、木に負担をかけない範囲で行う
品種別剪定のワンポイントアドバイス
すももやプルーンは品種によって生長のクセや剪定の注意点が少し異なります。代表的な品種ごとに、剪定のポイントを見てみましょう。
大石早生(すもも)
枝が多く出やすく、混み合いやすい樹形のため、毎年しっかりと間引き剪定を行い、日当たりと風通しを確保しましょう。
ソルダム(すもも)
果実が付きすぎる傾向があるため、摘果(果実の間引き)も併用し、樹勢を維持するのがポイントです。
スタンレイ(プルーン)
比較的剪定には強く、枝の更新を意識して整枝することで毎年安定した収穫が期待できます。
バーバンク(交雑種)
すももの性質を強く受け継いでいるため、横に広がる枝の整理を重点的に。果実が重くなりやすいため、支柱や誘引も考慮するとよいでしょう。
このように、同じすももやプルーンといっても、品種ごとに最適な剪定方法を理解することで、より良い結果につながります。
実がならない?剪定でやりがちな失敗とその解決法
よくある失敗:
- 花芽を切ってしまった → 花芽(丸くふくらんだ芽)を見分けて残す
- 切りすぎた → 樹勢が弱り、翌年に影響。2〜3割までに
- 切り口から病気に感染 → 雨の日を避け、癒合剤を塗布
最初は不安でも、「少しずつ・慎重に」が成功の秘訣です。
剪定後の管理のコツと肥料の与え方
剪定が終わったら、その後の管理で木の健康をサポートしましょう。
剪定後の管理
- 切り口の保護: 癒合剤で殺菌&乾燥防止
- 施肥のタイミング: 3〜4月に元肥(有機肥料 or 果樹専用肥料)
- 水やり: 地植えなら基本的に不要、乾燥が続くときは補水しましょう
- 病害虫対策: 定期チェックと早めの処置が重要
剪定後に気をつけたい病害虫対策
剪定後の果樹は一時的に抵抗力が落ちるため、病害虫の発生リスクが高まります。特にすもも・プルーンは、以下のような害虫や病気に注意が必要です。
よく見られる病害虫:
- アブラムシ:新芽や若葉に群がり、樹勢を弱らせる。
- カイガラムシ:枝や幹に寄生し、吸汁して木を枯らす。
- 黒星病・灰星病:葉や果実に黒い斑点ができ、商品価値を下げる。
これらを防ぐには、剪定後に殺菌剤や殺虫剤を散布するのが効果的です。また、風通しの良い樹形に整えることで病害虫の発生を未然に防ぐこともできます。
日頃から葉の裏や枝の根元をチェックし、異常が見られた場合は早めに対処しましょう。木酢液などの自然素材を使った防除法も、家庭果樹にはおすすめです。
すもも・プルーンの剪定|まとめ
すももやプルーンの剪定について本記事では解説しました。
- 剪定は「冬」が基本!適切な時期に行う
- 特性に合わせて剪定方法を変える
- 切りすぎない&剪定後のケアを忘れずに
果樹は1年の手入れで結果が大きく変わる植物なので、しっかりと剪定と管理を行って、甘くて美味しい果実を楽しみましょう!