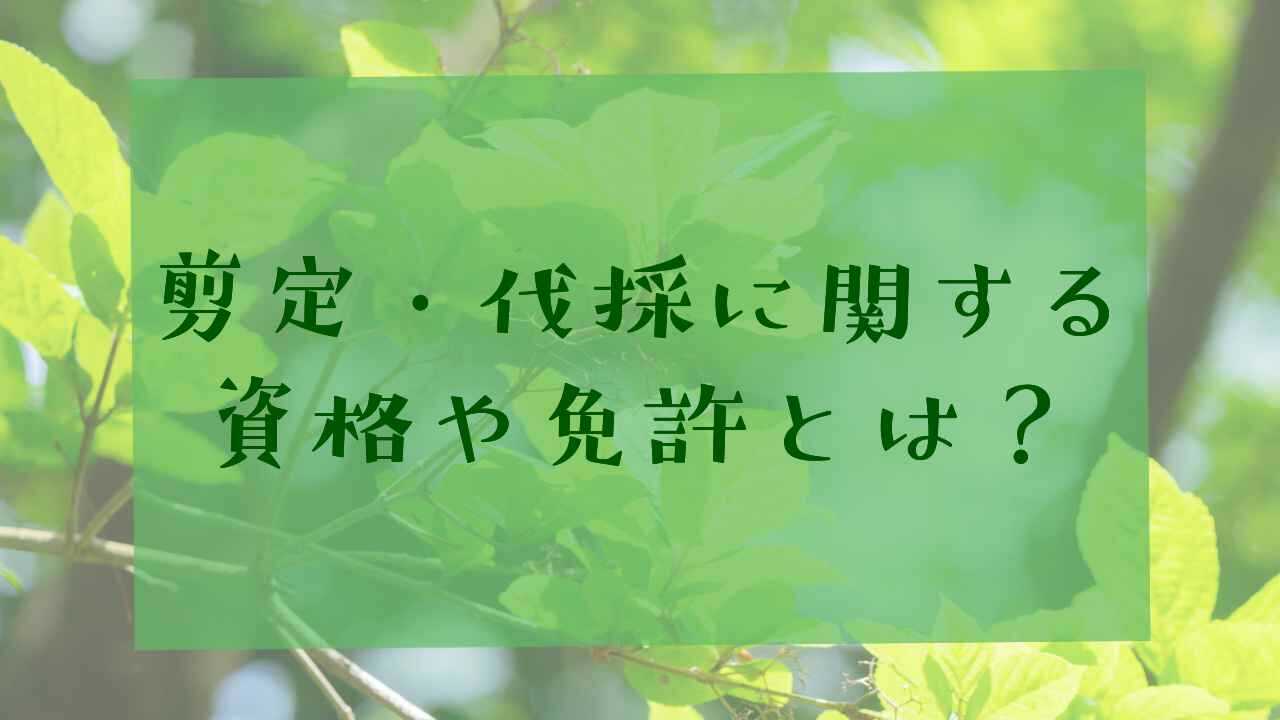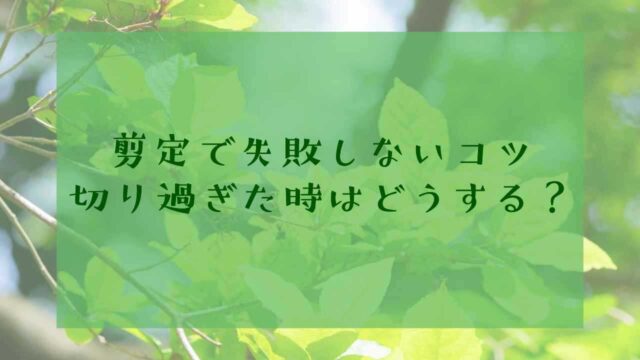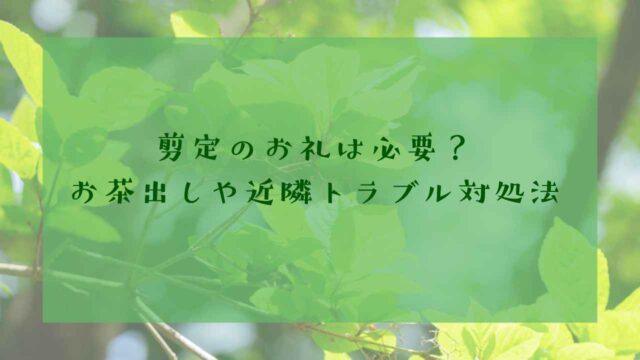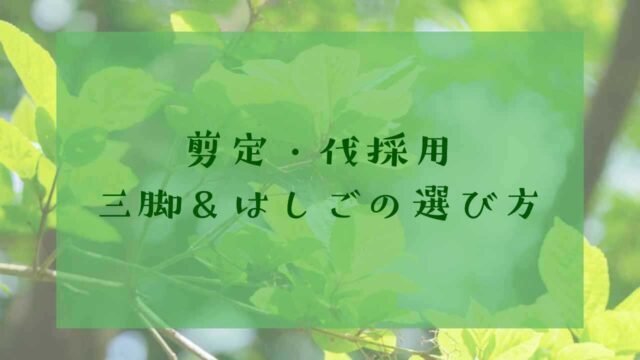剪定や伐採を依頼する際にどの業者に頼むか迷う事があると思いますが、特に資格や免許がなくても剪定・伐採業を行うことは可能です。
しかし資格や免許について予め知っておくと、依頼内容に応じてより良い業者の選定が可能になるため、本記事では信頼できる業者選びに役立つ、剪定・伐採に関わる主な資格や免許についてわかりやすくご紹介します。
剪定の仕事に関わる資格について
剪定の仕事に関わる資格でよく目にするものとして以下があげられます。どのような資格なのか詳しく見ていきましょう。
- 造園施工管理技士資格
- 造園技能士
- 剪定士
造園施工管理技士資格と造園技能士はよく似た呼称ですが、実は管理と実務どちらに重きをおくかが異なります。違いについて詳しく説明していきます。
造園施工管理技士資格(1級・2級)
1・2級造園施工管理技術検定資格は、国土交通大臣指定機関が実施する国家試験で、検定合格者には「造園施工管理技士」の称号が与えられます。
昭和50年にできた造園工事の管理を担当する専門資格で、工事の施工計画の作成や進行管理、安全対策の実施、工事品質の確認などを行います。
以下に受験のスケジュールを表にまとめました。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 3月中旬~4月上旬 | 受験申込(インターネット or 郵送) |
| 7月上旬(2級)・7月中旬(1級) | 第一次検定(学科試験)マークシート式 |
| 10月中旬 | 第二次検定(実地試験) |
| 12月下旬~1月 | 合格発表後、登録 |
2級の受験資格について
学歴や経歴により必要な実務経験年数が異なりますが、2級は実務経験があれば初めての方でも受けやすい入門資格です。
| 最終学歴 | 実務経験年数(例) |
|---|---|
| 高卒(造園・土木系) | 3年以上 |
| 高卒(他分野) | 4~5年以上 |
| 中卒 | 8年以上 |
| 大卒(造園・土木系) | 1年以上 |
1級の受験資格について
1級は責任ある立場を目指す方に求められる専門資格で、1級を目指すには原則として2級の取得後に一定の実務経験が必要です。
一次検定と二次検定に合格してはじめて1級を取得できます。
- 申込(3〜4月):勤務証明書・実務経験証明が必要
- 第一次検定(7月):マークシート方式。施工法・法規・環境など
- 第二次検定(10月):記述式。施工計画、安全・品質管理、工程表など
- 合格(12月〜1月):合格後は監理技術者として登録・現場に配置可能
2級を持っていない人でも、学歴と実務経験があればいきなり1級の受験も可能ですが、現場経験が重要です。
| 最終学歴 | 2級受験に必要な実務年数 | 1級受験に必要な実務年数 |
|---|---|---|
| 造園・土木系 大卒 | 1年 | 3年(2級取得後なら短縮可) |
| 造園・土木系 高卒 | 3年 | 5年(2級取得後なら短縮可) |
| 他分野卒・中卒など | 最長8年 | 8〜10年(実務内容次第) |
造園技能士(1級・2級・3級)
実際の造園作業を行う技能に優れた技術者を認定する資格で、技能検定は国(厚生労働省)が職業能力開発促進法に基づき実施しているもので、学科と実技の両方の試験に合格すると「技能士」の称号が与えられます。
植栽や剪定、石組みなどの高度な技術を駆使して、美しい庭園や景観を作り上げる役割を果たします。
取得方法:実技試験と学科試験に合格する
所定の実務経験があり、一定のレベルに達していれば誰でも受験可能です。
学科試験(正誤法による問題と4肢択一式問題)と実技試験(課題作成する作業試験と樹木名を判定する要素試験)があります。3級が初級、2級が中級、1級が上級という位置づけで、1級は7年以上、2級は2年以上の実務経験が必要です。1級・2級を持っていると上級の受験時に必要な実務経験が短縮されます。
剪定士
剪定士と呼ばれる資格には日本造園建設業協会が認定する以下の2つがあります。
- 街路樹剪定士
- 緑地樹木剪定士
街路樹剪定士は街路樹を剪定する作業者の知識および技術力を証明するもので、先に挙げた造園技能士であるか、剪定業務に直接従事した実務経験が7年以上ある者が、所定の研修を受講後、認定試験に合格すると取得できます。
緑地樹木剪定士は街路樹剪定士の知識と技術を基にした資格で、公園や緑地・公開空地・オープンスペースなど、街路樹以外の公共空間にある樹木を対象とした剪定のスペシャリストとして2023年に創設され、緑地樹木剪定士は街路樹剪定士でないとなれません。
大径木伐採に関わるチェーンソー資格について
大木(大径木)の伐採には危険も伴うため、大径木伐採に関わる資格について詳しく説明します。
チェーンソーによる伐木等特別教育
チェーンソーを用いて行う伐木・造材作業は、林業における死亡災害のうち約6割を占めるほど危険な作業であるため、業務で使用する場合は労働安全衛生法に基づいた特別教育を受講する必要があります。
なお個人でチェーンソーを使用する際は受講必須ではありませんが、受講すると作業の安全性を高めることができます。
取得方法:学科と実技の講習を受講する
受講資格は特になく、教習所に通うか講師を招いて以下の学科と実技の両方の講習を受ける必要があります。学科のみならWEB受講も可能です。
学科は以下の内容で合計9時間です。
- 伐木等作業に関する知識[4時間]
- チェーンソーに関する知識[2時間]
- 振動障害及びその予防に関する知識[2時間]
- 関係法令[1時間]
実技は以下の内容で合計9時間です。
- 伐木等の方法[5時間]
- チェーンソーの操作[2時間]
- チェーンソーの点検及び整備[2時間]
実技講習を終えると修了証が交付され、受講費用の相場は教習所によって異なりますが相場は約15,000〜25,000円です。
空師・アーボリストについて
少し聞きなれない言葉ですが、空師は伐採に関わる専門職として昔からある職業で、国外でも通用する資格のアーボリストについてもご紹介します。
空師
空師は、高所作業を専門とする伐採のプロで、日本では日本では数十人程度しかいない技術職です。
昔は高い建物が無く、木が一番空に近いもので、その木に登って作業をする、すなわち空に一番近いところで作業する職業ということで空師と呼ばれるようになりました。
寺社や民家の屋敷林のように、周囲に家屋等があると、木を横倒しにしたり、枝を落としたりすることができないため伐採の難易度があがり、街中ではビルや電線に近い木を安全に伐採する技術が求められます。
取得方法:弟子入りして修業する
明確な資格制度ではなく、師匠に弟子入りし指導を受けながら経験を積んでいきます。木登り以外にも木の性質を知り、伐倒の技術、状況判断能力を身に着けていきます。
アーボリスト
海外には、大きな木(8メートル以上)の維持と管理を専門とするアーボリストという職業があり、日本では「樹護士」と呼ばれています。
空師と同様に木の状態を把握し、適切な手入れを行う仕事で、アーボリストは木を意味するフランス語arbre(アルブル)が由来となっているそうです。
取得方法:認定機関で各種コースを修了する
日本国内でアーボリストとして活動するには、ISA(International Society of Arboriculture)、JAA(Japan Arborist Association)、ATI(Arborist Training Institute)による資格取得が推奨されます。
これらの資格は国際基準に基づいた樹木管理の技術を証明でき、行政や企業からの信頼を得られます。 習得内容には基礎知識を学ぶコース(BATシリーズ)や実践的な技術を磨くコース(AATシリーズ)、ロープ高所作業やレスキュー技術も含まれており、これらを修了することで、安全な作業が保証されるとともに、さらに上級資格への道が開かれます。
資格取得後も、ISAを通じて継続的な教育を受けることが義務付けられており、最新の知識と技術を維持するために、定期的な講習会や実地訓練が行われます。
樹木医について
樹木医とは、いわば「木のお医者さん」で、樹木医の仕事は多岐にわたります。
- 診断: 木の病気や害虫の被害、生育環境の悪化などを診断
- 治療: 病気の治療、害虫駆除、剪定など、木の状態に合わせて治療
- 予防: 病気や害虫の発生の予防対策
- 診断書の作成: 木の健康状態などをまとめた診断書を作成
- アドバイス: 木の管理に関するアドバイスを行う。
取得方法:実務経験を積み、選抜試験を受験する。合格後に研修と審査を受ける。
一般財団法人日本緑化センターが認定を行っている民間資格で、樹木の生理生態学、病害虫学、土壌学など、幅広い知識が問われます。
樹木医補資格と樹木医資格があり、樹木医補は樹木医補資格養成機関の登録を受けた大学を卒業すると認定を受けることができます。
樹木医試験の選抜試験を受けられるのは①樹木の調査、計画・設計監理、維持管理作業や診断・治療など樹木の保護・育成に関する業務経験が5年以上の方②樹木医補の資格を有し、認定後の業務経歴が1年以上ある樹木医研修受講者選抜試験に合格した方です。
さらに選抜試験の合格者が「樹木医研修」を受講し、実習及び資格審査(科目試験・樹種の識別に関する適性試験・面接試験)を経て樹木医資格を得ることができますが、5年毎の登録更新を義務化しており、登録更新の条件として所定の研修を受ける必要があります。
まとめ
剪定・伐採に関わる様々な資格・免許についてご紹介しました。
- 庭のお手入れを頼むなら確かな技術力を持つ造園技能士
- 高所作業は空師、病気の樹木の治療には樹木医に依頼