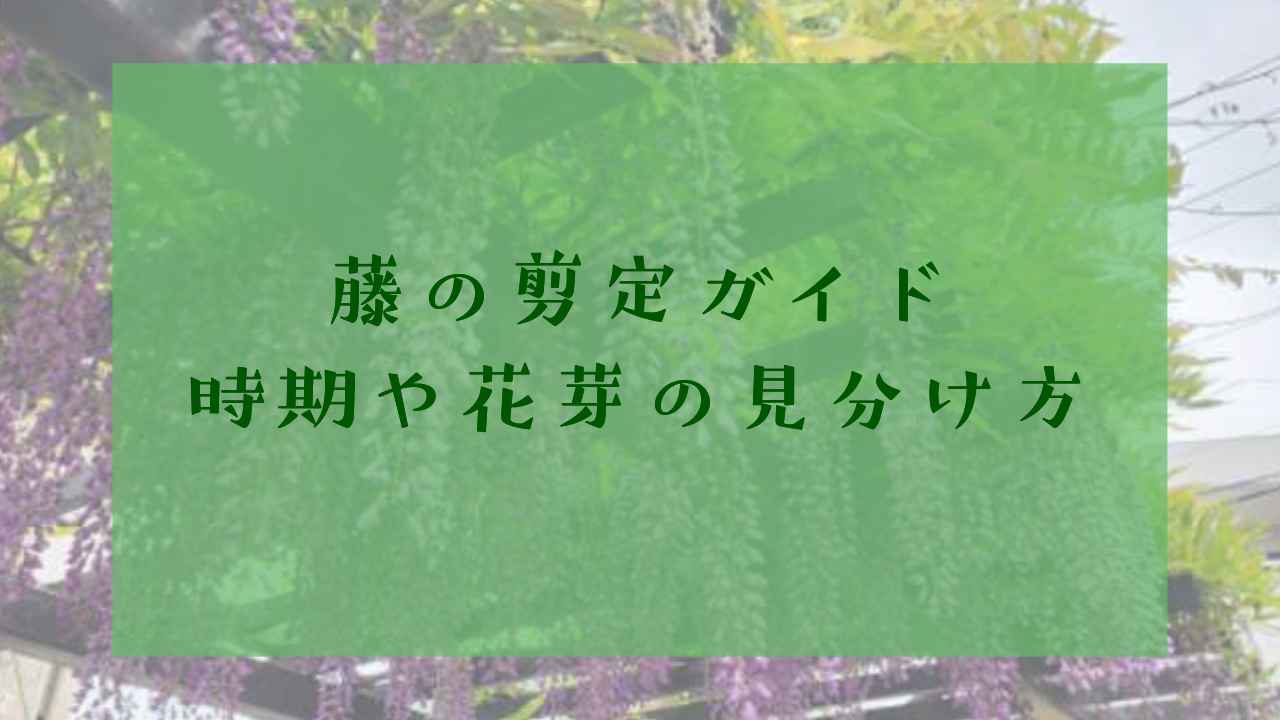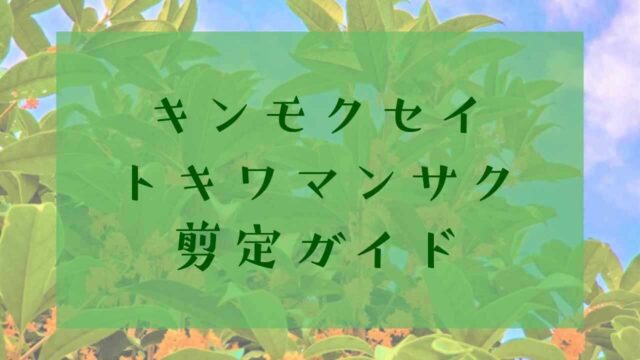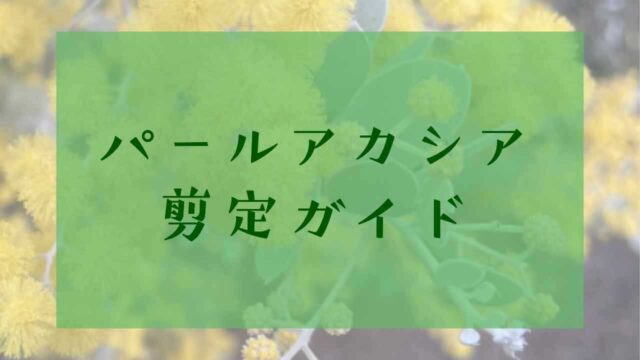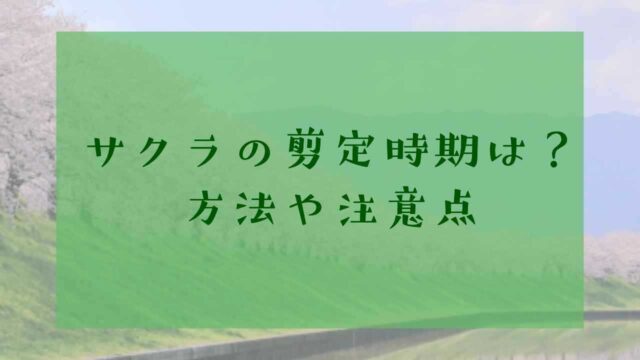藤は、その優雅な花房と甘い香りで、古くから日本人に愛されてきたつる性植物で、春の訪れとともに、棚から滝のように流れ落ちる紫や白の花々は庭や公園を華やかに彩ります。
本記事では、美しい藤を毎年咲かせるための剪定の時期、具体的な方法、さらには藤の種類ごとの特性や、鉢植えでの管理のポイントまで徹底的に解説します。
花木の剪定時期一覧表はこちらの記事をどうぞ!
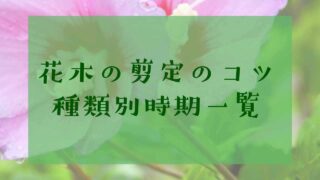
藤の剪定は開花後と落葉後の年2回
花後の剪定(夏剪定)
5月下旬~6月に行う夏剪定の主な目的は、咲き終わった花がらを摘み取り、新しく伸びたつる(新梢)を整理することで、翌年の花芽形成を促すことにあります。
藤の花が咲き終わった後、そのままにしておくと花房が実を結び始め、この実の形成には植物の多大なエネルギーが費やされるので、株が消耗して翌年の花付きが悪くなります。
休眠期の剪定(冬剪定)
11月下旬~3月上旬に行う冬の剪定は、藤が落葉し、枝の全体像がはっきりと見えるようになる時期に行い、この時期の剪定は、樹形を整えること、不要な枝を間引くこと、そして翌年の花芽の数を調整することに適しています。
休眠期に行う強剪定は、植物へのダメージが比較的少ないとされていますが、遅くとも2月初旬から3月上旬の芽出し前までが目安です。
まず枯れ枝、長く伸びすぎた枝、内向きに生えた枝、地面から直接生えてくるひこばえなどを、その付け根から切り取ります。
この時期には、翌年咲く花芽がすでに形成されており、葉芽に比べて大きく丸みを帯びているため、比較的見分けやすいですが、花芽を誤って切り落とさないよう注意しましょう。
1本の枝につき3~5個の花芽を残して切り詰めますが、特に短い枝は、花芽がつきやすい傾向があるため、切らないようにします。
落葉期は、つるの状態が最もよく分かるため、剪定と合わせて誘引作業を行うのに最適な時期でもあり、棚や支柱に沿ってつるを均等に配置し、紐などで固定することで、各枝に十分な日光が当たるように整えることができます。
剪定を避けるべき時期とその理由
7月~8月の剪定
この時期の強い剪定は、藤の生理サイクルに大きな影響を与え「狂い咲き」と呼ばれる季節外れの開花を引き起こし、株の生育に悪影響を与えることがあります。
もし夏剪定がこの時期までずれ込んでしまった場合は、無理に剪定せず、11月の冬剪定まで待つようにしましょう。
多くの花芽は、前年の夏(6月から9月頃)にかけて形成されることが知られており、この花芽形成期に不適切な剪定を行うと、花芽が失われたり、植物が花芽形成ではなくつるの伸長にエネルギーを集中させてしまうことがあります。
藤の剪定方法

藤の剪定において最も重要なのは、翌年の花を咲かせる花芽を正確に見極め、誤って切り落とさないことであり、この識別能力を養うことが藤の剪定を成功させるための鍵となります。
花芽と葉芽の見分け方
花芽と葉芽は、植物が休眠期に入り、葉が落ちた冬の時期に特に見分けやすく、夏(8月頃)には花芽が大きく膨らんでくるため、この時期から観察を始めるのも良いでしょう。
花芽は、葉芽に比べて大きく、丸く、ふっくらとした形状をしており、主にその年に伸びた短いつるの基部や、昨年花が咲いた短花枝と呼ばれる短い枝の元につく傾向があります。
葉芽は、花芽に比べて細く、尖っているのが特徴で、日当たりの悪い場所や、勢いよく長く伸びたつるの根元付近に多く見られます。
長いつるの切り詰め方と誘引のポイント
藤はつる性植物であるため、その生育を管理し、美しい姿を保つためには、つるの適切な切り詰めと誘引が不可欠です。
方法
藤棚や支柱に沿って、つるが重ならないように均等に配置し、シュロ縄などでしっかりと固定しますが、この際、藤の種類によってつるの巻き方が異なることを理解しておくと、よりスムーズに誘引できます。
例えば、日本の代表的な藤であるノダフジは「右巻き(上から見て時計回り)」、ヤマフジは「左巻き(上から見て反時計回り)」につるが巻く特性があり、この特性に合わせて誘引することで、藤の自然な成長を助け、より美しく仕立てることができます。
花がら摘みの重要性と手順
花がら摘みは、藤の剪定の中でも特に軽視されがちですが、翌年の花付きに大きく影響する非常に重要な作業です。
咲き終わった花をそのままにしておくと、その花房が実を形成し始め、植物は多大な栄養分とエネルギーを消費した結果、本来翌年の花芽形成に使うべきエネルギーが奪われ、株の体力が消耗し、翌年の花付きが著しく悪くなってしまうのです。
花がら摘みは、花房の付け根から2~3芽、または2cm程度の部分を残して手でカットしますが、この際、葉は残すように注意し、花房だけを丁寧に摘み取ることがポイントです。
たくさんの花が咲いた後、全ての花がらを取り除くのは根気のいる作業ですが、見つけ次第こまめに行うことで、藤の健康と翌年の豊かな開花を確実にサポートすることができます。
藤の種類:ノダフジ、ヤマフジ、アメリカフジ
剪定の基本的な考え方は共通していますが、種類ごとの特性を理解することで、より適切な手入れが可能になり、その藤が持つ本来の美しさを最大限に引き出すことができます。
日本固有種(ノダフジ・ヤマフジ)の特性と剪定の注意点
日本には主に「ノダフジ(Wisteria floribunda)」と「ヤマフジ(Wisteria brachybotrys)」の2種類の藤が自生しています 。これらは日本の風土に適応し、古くから親しまれてきました。
- ノダフジ
「藤」として広く認識されており、最大の特徴はつるが「右巻き(上から見て時計回り)」に伸びる点で、花房は20~90cmと非常に長く垂れ下がり、その壮麗な姿は藤棚などで見られます - ヤマフジ
ヤマフジは、つるが「左巻き(上から見て反時計回り)」に伸び、花房は10~20cmとノダフジに比べて短く、まとまった房状になるのが特徴です。また、葉の裏に毛がある、側小葉が少ないなどの細かな違いもあります
剪定の注意点
ノダフジは特に生育が旺盛で、つるが1年で2~3mも伸びることがあるので、藤棚や広いスペースでの誘引と管理が非常に重要になります。
強剪定は花芽を失うリスクがあるため、特に冬の剪定時には、花芽と葉芽の見極めがより一層重要で、つるの巻き方を意識して誘引するとより美しい樹形と花付きを促します。
アメリカフジ(二季咲き性)の特性と剪定方法
「アメリカフジ(Wisteria frutescens)」は、日本の藤とは異なる特性を持つ品種で、特に「アメジストフォール」などの園芸品種が人気を集めています。
特性
日本の藤(特にノダフジ)と比較して、花房が日本の藤のように長く垂れ下がることが少ないのが特徴で、つるの伸びが控えめなので広大な藤棚を必要とせず、支柱仕立てや鉢植えでも比較的容易に栽培できます。
また若木のうちから花をつけやすい性質があり、初夏(通常の藤の開花期)と晩夏(夏終わり頃)の年2回花を咲かせることが可能です。
剪定方法
アメリカフジの剪定も基本的には花後に行い、春から伸びたつるは、根元から2~3芽を残して7月頃に切り詰め、徒長枝は、見つけ次第間引くか切り戻します。
冬場の剪定は、直立して伸びすぎる枝や交差枝、枯れ枝など、樹形を乱す枝を切り詰める程度に補助的に行い、つる全体としては、根元から3~5芽を残して切り戻すのが目安です。
アメリカフジは日本の藤に比べて管理がしやすい傾向がありますが、二季咲き性であるため、花後の剪定を適切に行うことで、年に二度の開花を楽しむことができるでしょう。
鉢植えの藤の管理のポイント
藤は地植えだけでなく、鉢植えでも栽培を楽しむことができ、特に「一才藤」などの小型品種は、鉢植えに適しており、室内でも美しい花を咲かせることが可能ですが、地植えとは異なる特有の管理ポイントがあります。
鉢植えならではの注意点
鉢植えの藤は、限られた土壌環境で生育するため、根詰まりを起こしやすく、水切れや肥料不足になりやすい傾向があり、花付きに直接影響を及ぼすため、地植え以上にきめ細やかな管理が求められます。
剪定の基本
鉢植えの藤も、地植えと同様に、花後の夏剪定(5~6月頃)と休眠期の冬剪定(11月~3月頃)が基本ですが、5~6月頃に芽摘みを行い、葉を1枚残して残りをカットし、枝をコンパクトにまとめます。
冬の落葉期には、つるを整理して好みのサイズや樹形に整える思い切った剪定が可能ですが、花芽を落としすぎないよう注意しましょう。
水やり
生育期(4月から9月頃)の藤は特に水を好み、鉢植えの場合、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるようにしないと水切れを起こしてしまいます。
肥料
鉢植えの藤には、2月頃と花後に緩効性の化成肥料を置き肥として与えるのが一般的ですが、肥料が強すぎると、つるばかりが伸びて花芽がつきにくくなることがあるのでリン酸成分の多い肥料を選ぶと良いでしょう。
植え替えについて
鉢植えの藤は、地植えに比べて根が張るスペースが限られているので根詰まりを起こすと、水や養分の吸収が悪くなり、花付きが悪くなる原因となります。
時期と頻度
植え替えは、植物が休眠期から目覚める前、根への負担が少ない2月下旬から3月中旬頃の芽出し前に行うのが最適です。
若木の場合は2年に1回、古木の場合は3~5年に1回が目安とされていますが、鉢底から根が飛び出している場合は、すぐに植え替えを検討しましょう。
植え替えの際は、古い根を中心に整理し、若木の場合は多めに、古木の場合は控えめに根を切り、土は一般的な混合土を、鉢の大きさは、同じものか一回り大きいものを選びます。
藤は根を切られると一時的に弱ることがあるため、数年間花が咲かなくなる可能性もありますが、将来的な株の充実のためには必要な作業です。
剪定の失敗事例と対策
よくある失敗例とその原因
花芽を切り落としてしまう
特に、花芽が形成される夏の時期(7月~8月)に強剪定を行うと、翌年に咲くはずの花芽ごと切ってしまうことがあり、冬の剪定時も花芽と葉芽の見分けがつかずに誤って花芽を切ってしまうことがあります。
対策: 花芽と葉芽の見分け方をしっかりと学び、冬の落葉期に丸くふっくらした花芽を残すように意識して剪定し、7月~8月の花芽形成期は剪定を避けましょう。
適切な時期に剪定をしていない
剪定時期を誤ると、花芽が形成されなかったり、狂い咲きを起こして株が消耗したりします
つるの手入れを怠る、または強剪定しすぎる
藤のつるは非常に旺盛に伸びるので、放置すると混み合って日当たりや風通しが悪くなり、花付きが悪くなる一方で、花芽がつくられる夏の時期に強剪定を行うと、株がダメージ回復に栄養を使ってしまい、花芽がつきにくくなることがあります。
水、肥料、日光が不足または過多
藤は日光を好み、生育期には水を多く必要するのと、マメ科植物である藤は自分で窒素分を作り出すため、窒素肥料を与えすぎるとつるばかり伸び花付きが悪くなることがあります。
対策: 日当たりの良い場所に植え、生育期には水切れに注意し、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるのと、肥料はリン酸やカリウム成分が多いものを冬に与えます。
藤の剪定|まとめ
こちらの記事では藤の管理・剪定について徹底解説しました。
- 藤の剪定は年2回(花後の夏剪定と休眠期の冬剪定)
- 花がら摘みは、植物のエネルギーを無駄にしないために必要
- 花芽が丸くふっくらしているのに対し、葉芽は細く尖っている
- 花芽の誤切除や不適切な剪定時期、樹齢や環境要因により、花付きは変わる
この記事によって、あなたのお庭の藤が毎年見事な花を咲かせる一助となれば幸いです。