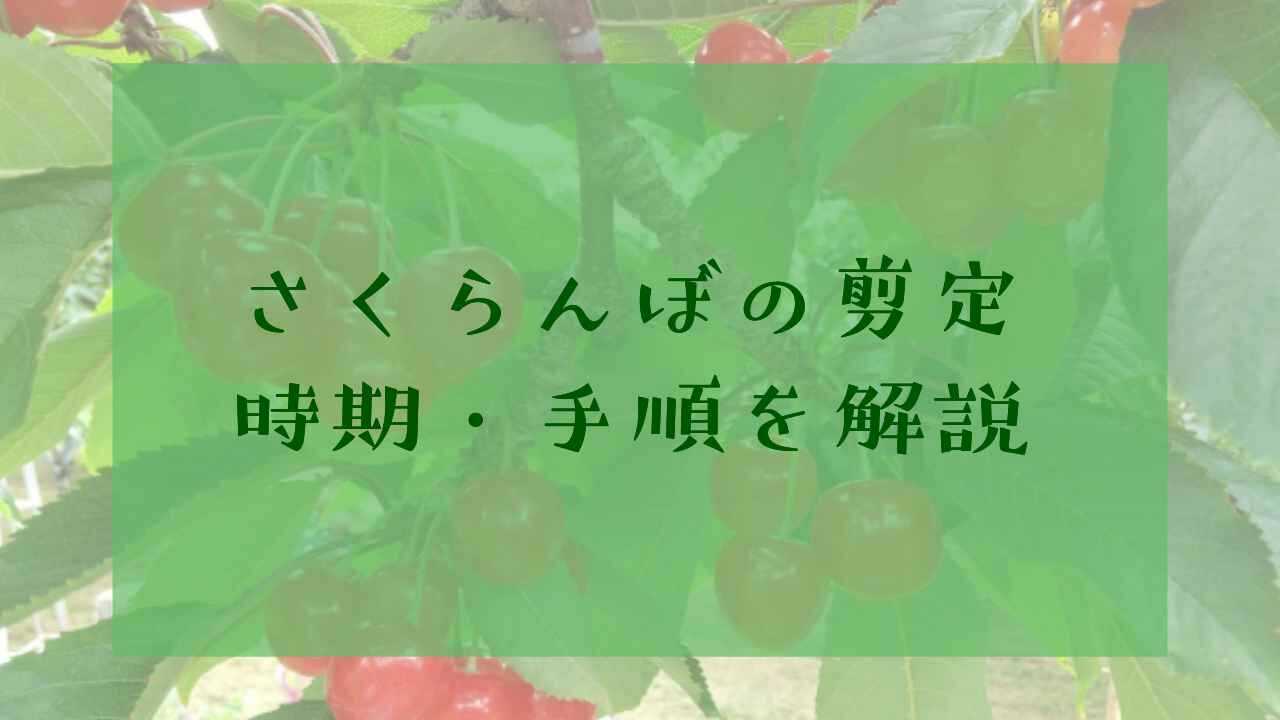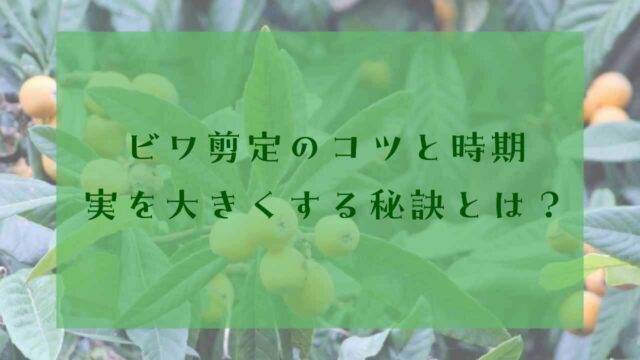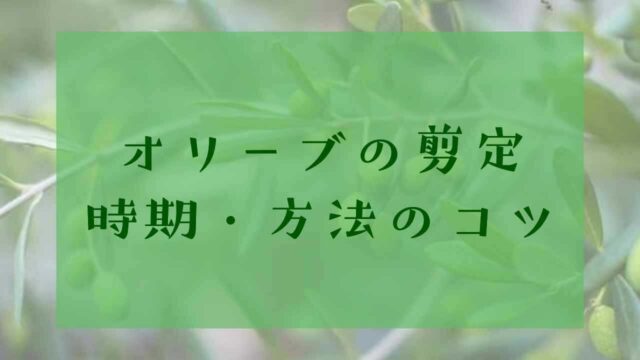春に白い花を咲かせ、初夏には赤くて甘酸っぱい実をつけるさくらんぼの木は、見た目の美しさと果実の楽しみを兼ね備えた人気の果樹です。
「果樹=管理が難しい」というイメージを持たれがちですが、さくらんぼは庭木や鉢植えとしても育てやすく、家庭菜園でも注目されています。
こちらの記事ではさくらんぼの木の剪定や育て方について解説します。
さくらんぼについて

代表的な品種には佐藤錦や紅秀峰などがあり、どちらも比較的コンパクトな樹形で限られたスペースでも栽培しやすく、実の収穫も楽しめる家庭向きの品種です。
さくらんぼの品種について
佐藤錦(さとうにしき)
収穫時期は6月中旬〜下旬で、栽培の難易度はやや高めで病害虫対策、剪定、水はけ管理といった栽培環境をしっかり整えれば、家庭でも高品質な実が期待できます。
- 果実:果皮は光沢のある鮮紅色。果肉はやわらかく、果汁が多い
- 味:甘みと酸味のバランスが絶妙で、完熟時には非常に香り高くなる
- 自家結実性がなく必ず別品種との組み合わせが必要
日本で最も有名な品種で、味のバランス・香り・美しさすべてにおいて優秀ですが、寒冷地向きの品種で、暖地では樹勢が落ちる傾向があるため要注意です。
紅秀峰(べにしゅうほう)
収穫時期は6月下旬〜7月上旬の晩成種で、大玉で糖度が非常に高く、収穫後も日持ちが良いため、近年では佐藤錦に次ぐ人気品種です。
- 果実:大粒・濃紅色で果肉がしっかりしており、裂果しにくい
- 味:酸味が少なく、糖度は20度前後にもなるほどで濃厚な甘さが特徴
- 自家結実性はほぼないため、ナポレオンや高砂など受粉相手が必要
気温が高めの地域でも育てやすい上、雨に強く裂果も少ないため、梅雨時期の収穫も安定しやすいですが、樹勢が強いので剪定で抑える必要があります。
ナポレオン
収穫時期は6月中旬〜下旬。受粉樹として非常に優秀で、日本での栽培の歴史は佐藤錦よりも古い、ヨーロッパ原産の伝統品種です。
- 果実の特徴:赤と黄色のまだら模様があり、果肉はやや硬めで加工にも
- 味:酸味がやや強めで爽やかでさっぱりとした風味で、加熱調理にも適する
- 自家結実性はないが、花粉の質が良く複数品種に使える
枝が広がりやすく、剪定で樹形をしっかり作れば非常に扱いやすい上に病気にも比較的強いので、1本目の品種選びに迷ったらナポレオン+他品種の組み合わせから始めるのがおすすめです。
高砂(たかさご)
収穫時期は6月上旬〜中旬の早生種で、実付きがよく、コンパクトに育てやすいため、家庭菜園初心者におすすめの代表品種です。
- 果実:小ぶりで鮮やかな赤色で、数が多くつき、収穫量も安定しやすい
- 味わい:甘みが強く酸味は控えめ、軽やかな味わいで、子どもにも人気
- 自家受粉しにくいが、他品種と一緒に育てることでしっかり結実する
受粉用・果実用のどちらの役割もこなせる万能選手なので、庭に1本は入れておきたい品種といえるでしょう。
山形美人(やまがたびじん)
収穫時期は6月中旬〜下旬で、病気に強く実の品質も高い、人気上昇中の新品種です。
- 果実:大玉で艶やかな赤色、裂果しにくく果肉はややしっかりめ
- 味:酸味が少なく糖度が高いので香りも良く、デザート向け
- 自家結実しないため、高砂や佐藤錦などとの併植が必要
樹勢が強く、病気や湿気にも強いため、初心者向けとしても優秀な品種といえます。
栽培環境について
日当たりは1日6〜8時間以上の直射日光が理想で、水はけの良い弱酸性〜中性の土に植え付け、乾燥と湿気のバランスに注意を払いつつ、鉢植えなら表土が乾いてきたらたっぷり水を与えます。
地植えにすると大きく成長して収穫量が見込めます。鉢植えならコンパクトに育てられるため、ベランダなどでも育てやすいというメリットがあります。
結実は植え付けから4~5年後が目安で、成木になると豊作が期待できます。
さくらんぼの剪定について
剪定の時期
剪定に適した時期は夏と冬
冬季剪定は12月から2月にかけて行うのが理想で、木が休眠期に入っている間に太枝を整理し全体の樹形を整えても、樹液の流れが止まっているため、ダメージが少なく済みます。
一方、夏季剪定は7月〜8月に軽く行うのがポイントで、春から夏にかけて旺盛に伸びた枝を整理して風通しを改善し、病害虫の発生を防ぎます。強く切りすぎると逆効果なので、あくまで整枝程度にとどめましょう。
避けるべき時期
3月〜5月の開花・結実期は、花芽や幼果が形成されている重要な時期であり、強剪定を行うと大切な花芽を切ってしまい、実がつかなくなる恐れがあります。
また、真夏の猛暑日や冬の霜が降りるような寒冷時期も、木に大きなストレスを与えるため剪定には不向きで、特に寒冷地では1月中に剪定すると寒害のリスクがあるため、2月以降の晴れた日がおすすめです。
さくらんぼ剪定のコツと手順
切るべき枝の見極め
さくらんぼの木には、剪定対象となる枝がいくつかあります。
- 徒長枝:見た目のバランスを乱すだけでなく、実がつきにくい枝
- 内向き枝:風通しを悪くして病気を招く原因になる
- 交差枝・重なり枝:こすれ合った傷から病原菌が侵入しやすい。
- 枯れ枝・細すぎる枝:養分を無駄に消費する
剪定の手順
- 全体の樹形を確認
開心自然形(主幹なしで枝を放射状に広げる形)・主幹形(1本の幹から段状に枝を出す形)をベースに、どの枝を残すか決める。 - 徒長枝を根元からカット
上に勢いよく伸びる徒長枝は、花芽がつきにくく、栄養を奪うので除去する - 交差枝・内向枝を間引く
他の枝とこすれたり、風通しや採光を妨げたりするので切る - 実をつけにくくなった古い結果枝は更新する
結果枝(花芽をつけた枝)は数年で更新が必要で、2〜3年目の枝を残す - 新しい結果母枝を育てる位置に切り戻す
元気な若枝の先端を1〜2芽残してカットすることで、新たな開花・結実を促せるが、花芽は前年の夏に形成されるため、剪定時に花芽の位置を確認して切りすぎないようにする
品種ごとの剪定のポイント
佐藤錦・紅秀峰
やや繊細なので剪定のやりすぎに注意が必要で、実をつけた枝の基部から若い枝を育て、更新剪定を計画的に行いましょう。
ナポレオン・高砂
樹勢が強く徒長枝が出やすいため、しっかり間引くことが重要で、毎年整枝してコンパクトに保ちましょう。
山形美人
成長は穏やかで管理しやすいが、日当たりを確保できるよう混みすぎないように剪定しましょう。
剪定後の管理と注意点
切り口の保護
病原菌や乾燥を防ぐため、特に太枝には必ず切り口に癒合剤を塗りましょう。
水やり・施肥
地植えは基本的に雨で十分ですが、鉢植えは表土が乾いたらたっぷり与えましょう。
肥料は、樹勢が強くなりすぎて徒長枝が出やすくなるため、春先の芽吹き時に有機肥料を少量与える程度でよいでしょう。
植え替え
鉢植えの場合は根詰まりを防ぐため、9~10月頃に一回り大きな鉢に植え替えましょう。
病害虫対策
黒斑病・カイガラ虫・カビ・鳥害に注意が必要なので、ネットや殺菌・殺虫剤を使用して予防に努めましょう。
年間の栽培スケジュール
| 時期 | 作業内容 |
|---|---|
| 12月〜2月 | 植え付け/冬の剪定/寒肥 |
| 春(開花期) | 受粉(人工授粉) |
| 5月〜7月 | 摘果、夏の軽剪定 |
| 5月・10月 | 肥料(鉢植えは年間3回) |
| 収穫期(5月中旬〜7月) | 色づいた実を丁寧に摘む。雨よけ対策も |
よくある剪定の失敗とその対策
花芽を切ってしまった
花芽は前年に伸びた枝の先端付近につくことが多いため、うっかり剪定してしまうと実がまったくつかない年もあります。
剪定前に芽の状態をよく観察し、花芽と葉芽を見分けながら慎重に作業することが大切です。
切りすぎてしまった
勢いよく切りすぎると枝数が足りず光合成が減り、木の体力が低下してしまい、特に夏季剪定で強く切りすぎるのはNGです。
剪定は全体の2〜3割以内にとどめることを目安にし、切りすぎたと感じたときは、追肥と水やりで木の回復をサポートしましょう。
さくらんぼの剪定|まとめ
本記事ではさくらんぼの剪定や品種による違いを解説しました。
- 初心者は病害虫に強く家庭向きの品種を選ぶ
- 冬の剪定をメインに、残すべき枝を見極めて切る
- 自家受粉しにくいので、2品種以上を育てるか人工授粉を行う
さくらんぼは家庭でも育てやすく、品種選びと剪定のタイミングを押さえれば毎年おいしい実を楽しむことができるので、本記事を参考に育ててみてください。